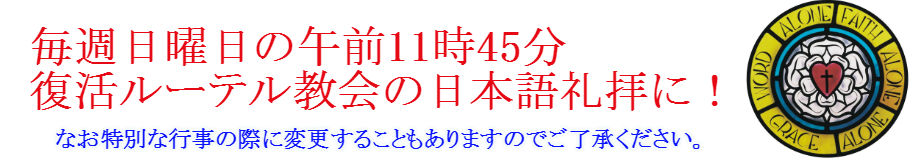ヨハネ 1:43-51
主の恵みと平安が豊かに、あつまった会衆の上に、また今日の御言葉をウェブサイトを介して読まれる世界中の兄弟姉妹にも、また事情があって今日の礼拝に来られない方々の上にも、同じ主の恵みが、また、憐れみが豊かに注がれますように。
それぞれ、教会に来られるようになったきっかけはなんだろうか?だれかが話しかけた言葉が大きなきっかけになっているということがあると思う。もちろん、その言葉をかけてくれた人は重要だと思う。 しかし、その語った言葉はなんだっただろうか?
私たちが、普段からだれか教会に来て欲しいと誘うにしても、どういう風に話したら良いかよくわからないのが現実ではないかと思う。今日の御言葉をじっくり聞く中で、そして、とくに日本人社会では、キリスト教もひとつの宗教にしかすぎなくて、信じられないと心の奥底では思っている方々に、どうやってキリスト教を紹介したらよいかという参考になるのだと思う。
さらに、教会に来て、一番最初に気づかなければならないことは、なんなのか? その気づきによって、なにが起こるのか? キリスト教を信仰するようになる最初の一歩は何なのか? そのようなことについて考える良い機会になるのだと思う。
与えられた福音書は、ヨハネ一章43節から。ヨハネ福音書ではイエスの最初の弟子は、アンデレとその兄弟ペトロだったことが、少し前の35-42節に書いてあった。そして、今日の聖書箇所では、その次に弟子になったのが、フィリポとその友人と思われるがナタナエルである。
フィリポはイエスに会って、「私に従いなさい」と言われると、あっと言う間にその方こそ、聖書の中でモーセもまた預言者たちも、記述していた方だとわかる。 つまり救い主だといえる人は、ナザレ出身のヨセフの子でイエスだということがわかった。
そして、すぐに、そのことを、友人ナタナエルに話す。しかし、ナタナエルは疑う。ナザレからそんな人が出るわけない。それはやや問題発言だと思う。 ナザレとかガリラヤ湖畔の町々、どういう町だったかわかりにくかもしれないが、ナザレは貧困都市、ガリラヤ湖畔は、それに比べ、中級とでもいえるイメージがあったのかもしれない。 だからナタナエルは、「へっ、ナザレなんかから救い主なんか出るもんか」という偏見があったのだと思う。
しかし、フィリポは、そのナタナエルの偏見をとがめるでもなく、また議論をするでもなく、自分ではイエスがどういう人だと思っているかのみ話しただけで、単純明快に、「来て、見なさい。」という言葉でナタナエルにイエスに会うことを薦める。
そして、ナタナエルは、イエスの方に向かっていく。 すると、イエスは偏見のあったナタナエルなのに、「これこそまことのイスラエル人だ。正直な人だ。」という言葉を語る。
ナタナエルはびっくりする。そして、イエスは、ナタナエルのしていた事、いちじくの木の下で考え事をしていた事を知っていたし、また、その考え事が、おそらく旧約聖書の創世記でヤコブが夢で見ていた光景だったのではないかと思われるが、見事に知っていた。
今週の聖書日課では詩編139編が与えられているが、新約聖書から時代を遡って1000年近く前のダビデも、またその後の詩編作者たちも、いかに神がすべてをご存知あるかを詠っている。何をしていようが、何を考えていようが、それをずばりわかっておられるお方、主なる神がおられることを詩編で詠っていた。
そして、ナタナエルも、まさにそれを実感したのだろう。 友人のフィリポはなんら議論することはなく、ただ「来て、見なさい。」という言葉を述べただけで、ナタナエルはイエスと出会い、偏見の持ち主だった彼が、すべてをご存知である主によって、ひっくりかえされ、悔い改めて、イエスに従うものに変えられた。
今日の福音書箇所から、私たちは何を学んでいるのだろうか? 同胞の日本人に伝道するとき、やはりイエスのことを信じてもらえないという大きな壁があるのだと思う。そのような壁に対して、熱心に議論するより、はるかに、単純に、イエスのところに「来て、見て」ということがとても大切なように思う。
それはイエスの聖霊によって成り立っている教会に来ることの大切さがあるのではないだろうか? 漂う聖霊と遭遇する中で、いかに自分が、かたよった考えや、偏見をいただいていたか、あるいは自分勝手な考え方をしていたかに気がつかされる必要があるのだと思う。
それは未信者の人ばかりではなく、先週は礼拝に出て清くされて礼拝堂から送りだされたが、世の荒波にもまれて、1週間後に礼拝に戻ってきたキリスト信者とて、同じことなのだと思う。 そこには、私たちの中に、間違いや罪、神への疑いや背信をおかしてしまっていたというのが正直なところなのだと思う。 いや、私はそんなことはない、という人がいたら、それがまさに過ちの証拠なのだと思う。
礼拝で最初の讃美歌を歌った後は、まず罪の告白、悔い改めである。 現在用いられている式文のなかでは、私たちの心がどういう状況にあるのか、また、どういうことをしたいと思っているかもすべてご存知の神の御前で告白しましょう。と司式者が述べている。すべての世界中のキリスト教会のリーダである聖霊なるキリストが、心の奥底までご存知であることに気づくことがいかに大切か、そして、悔い改める、神に向き直ることこそ、クリスチャンとしての第一歩である。 そしてその一歩は礼拝に来る度に、同じように悔い改めるのが信仰生活の持続なのだろう。 しかし、この悔い改めは私たちが友人同志で強制できるものではない。 だから、フィリポの言った「来て、見て。」と単純に誘うことの大切さがあるのだと思う。
アーメン
安達均
“Come and See”
John 1:43-51
May your Grace and Mercy be poured into the hearts of the people gathered in the sanctuary, the people who are not able to come to worship today, and the people who read this message through the website! Amen.
What triggered you to come to church? I believe that someone, whether it be a friend, relative, or spouse, invited you originally. Of course that invitation is important, but do you remember how they invited you?
In our mourn of faith, we often desire to invite others to church. In practice, many of us struggle with how we invite them. In listening to the word of God, we are given a great hint on how we may invite people — Especially those who believe that Christianity is like any other religion and along with it comes the untrustworthiness associated with cult followings.
Today’s gospel provides an opportunity to reflect on the first thing that we should realize as followers of Jesus, and consequently teaches us what we should do. In other words, it lays out the first step to take in following Jesus after his invitation.
The Gospel text is John 1:43-51. The first two disciples out of twelve were Andrew and his brother, Peter, that was written in verses 35-42. In today’s text, the third and fourth disciples appeared, Philip and Nathanael.
When Philip met Jesus, he immediately could see that it was Jesus from Nazareth, the very person the messiah, Moses, and the prophets wrote about! When Nathanael heard the news, he was suspicious saying that the messiah won’t be from Nazareth. The context at play makes this a prejudice assertion. Although we do not have a full understanding of the cultures of these villages, it seems that Nazareth was known as a poor city. The villages along Lake Garalee were more affluent, perhaps comparable to the modern example of cities like Newport Beach, Laguna Beach, or Dana Point. Nathanael looked down on Nazareth because of his prejudice, and saw there was no conceivable way that the messiah would be from Nazareth.
However, Philip graciously handled the evident prejudice by saying these simple and clear words: “Come and see for yourself.” So Nathanael began his journey to find Jesus.
Even though Jesus was aware of Nathanael’s skepticism, he endorsed Nathanael when they first met. “You are a genuine son of Israel—a man of complete integrity.”
Nathanael asked how he knew. The conversation continued and Nathanael came to the realization that Jesus knew everything from where he was (under the fig tree) to what Nathanael was thinking (he was pondering the scene of what Jacob saw as written in Genesis.)
This past week, from Thursday according to the lectionary, Psalm 130 was given to us. In that Psalm, the king David, B.C. 1000, and people after sang that God knew everything, where they were, what they did, what they thought, and what they would do.
I believe Nathanael thought the same way as soon as Jesus said a few words to him. This was triggered from Philip’s testimony and a simple invitation. “Come and see [for yourself].” As soon as Nathanael met Jesus, the skepticism was gone, he repented, and became a follower of Jesus Christ.
Today’s Gospel story shows us how to tackle the wall of skepticism that religions are assumed to have. It is far more important to give a simple invitation, “Come and See for yourself,” rather than arguing or trying to convince someone to become a believer.
Being exposed to the Holy Spirit within the walls of the church is a vital part of embracing the Christian spirituality. I have witnessed the shift in people’s beliefs at the very moment they enter the sanctuary and the sound of the organ. Through immersion in the Holy Spirit, one realizes their sins and is able to repent.
However, this also applies to all believers of the faith, not just those new to this religion. We come back to the sanctuary on a weekly basis and are given insight intohow we may have done the wrong thing, thought sinful things, or said hurtful things to someone. If there is someone who claims to be perfect and right, it is simply not true.
In our recent liturgy, the presider of the service states, “In the presence of God, who sees our hearts and our minds, let us confess our sin.” We confess our sins and repent at the beginning of the communion service. God, the ultimate presider of the church in the world, Jesus Christ, and the Holy Spirit know everything about what we do, think, and intend to do. If we truly internalize that God knows everything, it stands to reason that we admit and seek forgiveness regarding our sins because we are imperfect.
However, it can be very difficult to communicate the importance. Sometimes, the easiest thing to remember is the simple statement Philip made to Nathanael: “Come and See for yourself.”
Amen.
Pr. H. Adachi