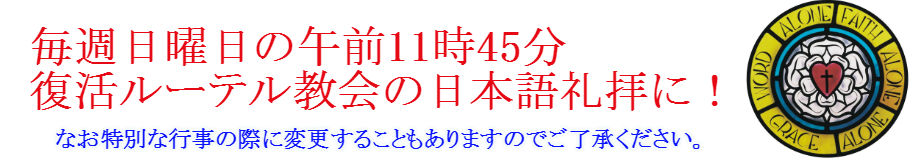ルカ 1:39-45
祈り:待誕節第四主日に礼拝に集められ感謝します。語られる言葉が主の思いに適うものでありますように。
井戸端会議という言葉がある、どういう意味で使われているだろうか?あまり良い意味に使われていないような気もする。 もともとは、水道がなかった時代に、井戸に水を汲みにきた女性たちが、長い時間にわたって、うわさ話をしたり、女性同士でいやみをいうこともあったのだろう。 そのような会話をするということで、たとえ井戸がなくても井戸端会議という言葉がいまだに使われている。
しかし、本当に、井戸の周りに集まって、あるいは現代であれば、街角やスーパーでいろいろな話をすることは、好ましくないことなのだろうか? 現実問題、この復活ルーテル教会の礼拝に集まる方々は女性が多いが、教会に集って、礼拝の前後にぺちゃくちゃ話しをする。 現実問題として、そのような会話の中には、「あんなこと話さなければよかった。」と反省する方がよくおられる。
しかし、良い話もいっぱいあるのだと思う。 そのような会話の中で、元気づけられて、今の自分がある。 本当にどん底にいたけど、あの時、希望が持てた。 等々、たくさんあるのだと思う。
井戸端会議で、今日のメッセージをはじめたが、聖書の世界において、井戸はとても大切な場所だ。現代でこそ、都会ではほとんどみなくなった。 しかし、聖書の世界では、人々は、水を得るのに、井戸にでかけて行った。 そして、実際、聖書の時代にも井戸端会議はあったのだろう。
旧約聖書、新約聖書と通して、水を汲みにいくのは、女性の役割だったといってよいだろう。 だから、ヨハネ4章で、サマリアの女性とユダヤ人の男性イエスが出会って話をするのは、異例中の異例だった。過去に5回も離婚してしまったサマリアの女性は、多くの人々が水を汲みにくる朝夕の時間帯を避けて、水を汲みにきている。そこには、いわば井戸端会議に参加したくない、井戸端会議でいやみを言われるようになりたくないという気持ちがあったのだろう。
さきほど読んだ聖書箇所、女性同士の会話だ。与えられた聖書箇所の少し前には、天使ガブリエルから、結婚をしていないマリアが、神の子をさずかることを聞く話が書かれている。 ここで、マリアはとても複雑な思いもあったであろう。 世間からは、いいなずけのヨセフがいるのに、他の男性と交わったとして、殺されるかもしれない。 あるいは、逆に、世界最高の宝くじがあたったようにも思えたかもしれない。
そのようなマリアは、ガブリエルから教わった不妊の女といわれたが身ごもることができた親戚のエリザベトを訪ねる。 エリザベトは結婚していた。 ただ、もう子供はできない、50半ばをすぎたような年齢まで子供ができなかった女性だった。しかし子供が生まれることになったという意味では、異常ともいえる話なのだろう。 しかし、ガブリエルの語った「神にできないことはない。」という言葉に、マリアは多いに力づけられたのだろう。
そのような状況の中で、マリアは三ヶ月間、エリザベトの家に滞在する。 かなり長い期間だ。 この女性同士は、当時の生活様式から考えて、いっしょに、井戸に水を汲みに行くというようなことも当然あったと思われる。 しかし、彼女たちの会話は、現代、私たちが 使っている井戸端会議のような会話ではなかった。
エリザベトは「結婚もしてないのに、妊娠なんかして、いったいどうなんてんのよ。」というような話はしていない。あるいは、マリアが神の子をさずかるという話から、私は祭司ザカリアとの間に何年もかかって妊娠できだが、マリアは神の子をいきなり妊娠したわけで、そこに嫉妬心をいだいたりするようなこともなかった。
マリアの話を聞き、自分のおなかの赤ちゃん踊るのがわかったエリザベトは聖霊に満たされて、「マリア、あなたは女性の中で最も祝福された方」(41節)と声たからかに言う。 また、「主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう」と話す。
そこには、エリザベトもマリアも、ガブリエルを通して与えられた神の言葉を信じ、神の約束が自分たちに起ころうとしていることを分かち会うということが、ともに井戸に水を汲みにいったり、食事をする中で、起こったことを聖書は伝えているのだと思う。 そこには、神の言葉を信じる者の、分ち合いの根本が描かれている。 そして、それは現代の教会で起こる会話の根本でもあるのだと思う。
与えられた聖書の御言葉、マリアとエリザベトの話は、現代の私たちの教会生活にも密着しているような話だと思う。 私たちは、人間が肉体的に生きていくのに、水が必要なように、精神的・霊的に満たされていくには、命の水、命の源となる神の言葉が必要だ。 だから人々が井戸に出かけるように、わたしたちも、命の水が湧き出る、つまり聖霊とともに、神の言葉が湧き出る、礼拝に集う。
そして、教会に集まって、神の言葉を聞き、その言葉を信じる者同士が、自分たちに起ころうとしている神の約束をわかちあうということがおこっている。 その一連の、神の言葉を聞き、分ち合いをするなかで、たとえ悲しいくつらい体験だったり、あるいは恥ずかしい体験をした1週間だったとしても、御言葉を聞き分かち合いをするなかで、新しい1週間に向けて、希望と喜びを持って、歩みだせる。
今日、みなさんは、この礼拝堂という、命の水が湧き出る井戸、泉のようなところに来られた。 そして、神の言葉をいただき、聖霊に満たされた。 クリスマスイブ、そしてクリスマスを迎える、この1週間、神がそれぞれに、どのようなことを実現しようとしているのか、思いをめぐらせていただきたい。 12月24日のクリスマスイブに、また、12月27日の日曜日で、元気をいただけるこの礼拝堂で会いたい。
Not Just Chatting Beside a Well
Luke 1:39-45
Let’s pray: Dear Lord, thank you for gathering us together on this Fourth Sunday of Advent. We pray that my meditation and spoken words are filled with the Holy Spirit and guided by your will. In Jesus’ name we pray, Amen.
There is a phrase “Idobata Kaigi” which literally means “A meeting beside a well” or “Chatting beside a well.” However, for Japanese people, what impression do you have about “Idobata Kaigi?” Most probably, you have a negative impression about this phrase. Historically, women gathered around a well and chattied with each other for many minutes…or even sometimes for hours. The conversation could become “gossip” or sometimes they criticized each other. Therefore, “Idobata Kaigi” is translated as gossiping in English.
However, is it always a bad thing for people, or women, to chat or speak with each other beside a figurative well? Are those conversations most often about negative matters?…or can they be positive? At Resurrection Lutheran Church, Japanese ministry, we have more women than men. And many women chat with each other before and after worship. I know that there are several people who confessed that they repent about inappropriate comments in the past and wish they could take them back.
I think there are many good conversations though, too. By having conversations, somebody thinks that because of the words Mrs. A said, they are truly encouraged, or transformed, or could walk toward the future with hope.
I started this message discussing Idobata Kaigi. During the ages the Bible was written, wells were always very important. In the last century, the number of wells dug was dramatically reduced because of modern water infrastructure of cities, but 2000 years ago and also before Christ’s time, wells were places physically and socially important for people’s daily lives. Wells were not only places to get drinkable water, but also places for important conversations.
In the New Testament age, women were almost always responsible for getting water from wells. Therefore, in John Chapter 4, during daytime, when the Samaritan woman met with the male individual, Jesus, it was a strange thing. The woman who was five-times divorced did not want to visit the well during daytime because she did not want to see other women. If she went in the morning, other people might make mean comments about her five divorces. From the Biblical story, mentioned in John Chapter 4, something similar to Idobata Kaigi was happening at that time.
Now, let’s think about the conversation between two women, Mary and Elizabeth, today’s good news given to us. A few verses before what I read, Mary listened to the Angel Gabriel. The Angel told Mary that even though she was unmarried, she would become pregnant and give a birth to the Son of God. Mary was puzzled and pondered what the angel’s words meant. She might have thought that she would be killed because people could assume that she had an inappropriate relationship with a man rather than remain chaste for her fiancé Joseph. On the other hand, she might have thought that she won the most valuable lottery in the world.
Then Mary decided to visit Elizabeth who was pregnant despite being told she unable to conceive. Elizabeth was married but was over 55 years old and it was impossible for her to get pregnant. But the Angel Gabriel said, “No word from God will ever fail” and this encouraged Mary tremendously.
In these circumstances, Mary visited Elizabeth for about three months. Considering that time period, the women most likely visited a nearby well together. They might have chatted beside the well, but their conversation was not like the ones normally associated with Idobata Kaigi.
Elizabeth did not say, “Why are you pregnant, Mary, what really happened to you?” or say anything mean to her, or feel any jealousy because Mary was pregnant so young and give birth to the Son of God.
When Elizabeth listened to what Mary said, Elizabeth’s baby jumped in her womb and she was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she screamed “Blessed are you among women.” (Verse 41) Then “Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her.” (Verse 45).
The Bible is informing us that both Elizabeth and Mary believed what God told and promised them through Gabriel and shared with each other what was truly happening to them. They shared things with each other, during that three months, while living together and visiting a nearby well. I think this sharing is the root of believers’ conversations happening in the Christian Church.
The Gospel text given to us today is strongly related to our lives in our church. Like we need water in our physical lives, we need the living water, the root of our spiritual lives, to maintain emotional and mental wellbeing. Therefore, we come to this sanctuary where abundant words of God, the living water, flow.
We gather for the worship service and listen to the word of God then we share with each other about how God is working in our lives. These listening and sharing occasions encourage us enormously to live a new week with hope and joy even if during the past week we might have experienced tough or shameful things.
Today each one of you came to this sanctuary where the living water abundantly flows. You listened to the word of God which is the promise of the Lord, and you are filled with the Holy Spirit whether you believe it or not. This week, we celebrate Christmas Eve and Christmas, please consider what Christmas means to you and what God wants to realize in you. And please share these realizations with your brothers and sisters. Amen.
Pr. H. Adachi
アドベント、待降節、の最終日がクリスマスイブ。聖書日課では、クリスマスイブに詩編96編が与えられている。 今年のアドベントの最後の主日を迎えるにあたって、詩編箇所96編をじっくり読もう。 そしていつものように、気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神は、現代の私たちに何を語っているのか、思いを巡らせよう。
詩編96編
1:新しい歌を主に向かって歌え。全地よ、主に向かって歌え。
2:主に向かって歌い、御名をたたえよ。日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。
3:国々に主の栄光を語り伝えよ/諸国の民にその驚くべき御業を。
4:大いなる主、大いに賛美される主/神々を超えて、最も畏るべき方。
5:諸国の民の神々はすべてむなしい。主は天を造られ
6:御前には栄光と輝きがあり/聖所には力と光輝がある。
7:諸国の民よ、こぞって主に帰せよ/栄光と力を主に帰せよ。
8:御名の栄光を主に帰せよ。供え物を携えて神の庭に入り
9:聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。全地よ、御前におののけ。
10:国々にふれて言え、主こそ王と。世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。主は諸国の民を公平に裁かれる。
11:天よ、喜び祝え、地よ、喜び躍れ/海とそこに満ちるものよ、とどろけ
12:野とそこにあるすべてのものよ、喜び勇め/森の木々よ、共に喜び歌え
13:主を迎えて。主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き/真実をもって諸国の民を裁かれる。
インパクトのある言葉として、10節から13節の言葉を挙げたい。
詩編作者の気持ちを想像しながら、詩編96編に書かれていたことを簡単にまとめたい。 1-3節では、すべての国の人々に新しい歌を歌って、主を賛美するように、呼びかけている。 4-6節では、主が天を造られたという、主を賛美する最大の理由が詠われていると思う。 7-9節では、だから主にひれ伏し崇拝するように。 以上9節までは、過去にも「詩編を読もう」でとりあげており、過去の記録を参考にして9節までのまとめを上記に再び書いた。10節以降は、「詩編を読もう」でははじめてとりあげているが、ドキッとすることを詠っている。すべての国々の王である主が、公平に裁くために来られる。だから天も地も、海とそこに住むものも、野とそこに存在するものも、すべて喜んで歌え! 主が来られて、世界を、そして諸国の民を、正しく真実をもって裁かれるのだから!!
さて、この詩編96編を通して、主なる神は現代を生きている私たちに、今日、何を語っているだろうか? 表題に「戦争なんかやめて喜び歌え」と書いた。キリスト教徒にとって、本日クリスマスイブを迎えている。世界中では残念ながら国々が戦争をしてしまっている、あるいは民族が民族に敵対してしまっている、そのような状況にある。その中で、全知全能で、全宇宙を治められる主なるお方が、ご自分の創造してものすべてに対して、戦争なんかしている場合ではなくて、救い主の到来を覚えて、喜び、歌うように語っておられる。 第二次世界大戦中の実話として、クリスマスに際して、世界各地の戦場で、戦争を休止したということがあったと聞く。 しかし、与えられている詩編は、クリスマスだから、あるいは12月24日のイブだから、戦争をやめるようにとは詠っていない。キリスト教の教えるクリスマスとは、たしかに、神のみ子は、この世に来られたが、まだこれからも来られる、第二の到来があるから、それに備えるようにという意味も含んでいる。だから、今日以降ずっと、キリストの第二に到来に備えて、戦争なんかしている場合ではなくて、常に喜び歌っているように、詩編は導いているのではないだろうか?
ミネソタ管弦楽団でチェリストとして活躍している磯村幸哉さんという方がいる。私は、セントポールにあるルーサー神学校在学中、磯村ご夫妻にはお世話になり感謝している。幸哉さんのお父様という方は、第二次世界大戦の体験から、子供たちには、武器など担いで世界に行って欲しくない。そして武器の代わりに楽器を担いで、世界に羽ばたくように、と教えたそうだ。幸哉さんのお兄様、和英氏は、東京カルテット(ニューヨークにある室内管弦楽団)の創設メンバーの一人でヴィオラ奏者。 またもう一人の兄弟が、ヨーロッパで音楽家として活動していると聞く。磯村ご兄弟の父上に、詩編96編の作者の思い、神の思いが、働いていたように思う。
安達均
アドベント、待降節、あっという間に第四主日になる感じがする。今年のアドベントの最後の主日を迎えるにあたって、17日から20日までに与えられている詩編箇所80編1-8節をじっくり読もう。 そしていつものように、気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神は、現代の私たちに何を語っているのか、思いを巡らせよう。
詩編80編
1: 【指揮者によって。「ゆり」に合わせて。定め。アサフの詩。賛歌。】
2:イスラエルを養う方/ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ/御耳を傾けてください。ケルビムの上に座し、顕現してください
3:エフライム、ベニヤミン、マナセの前に。目覚めて御力を振るい/わたしたちを救うために来てください。
4:神よ、わたしたちを連れ帰り/御顔の光を輝かせ/わたしたちをお救いください。
5:万軍の神、主よ、あなたの民は祈っています。いつまで怒りの煙をはき続けられるのですか。
6:あなたは涙のパンをわたしたちに食べさせ/なお、三倍の涙を飲ませられます。
7:わたしたちは近隣の民のいさかいの的とされ/敵はそれを嘲笑います。
8:万軍の神よ、わたしたちを連れ帰り/御顔の光を輝かせ/わたしたちをお救いください。
気になる言葉、インパクトのある言葉は何だろう? 私にとっては、アドベントにあって、2節3節に使われている「顕現してください」と「来てください」とい言葉。
詩編作者の気持ちを覚えつつ詩編80編を振り返りたい。1節に、< 「ゆり」に合わせて。> と書いてあり、ユダヤ教でゆりの花を飾った礼拝があったのかと思う。80編以外にも、45編、60編、69編でこの言葉が使われている。1節の最後には、「賛歌。アサフの詩。」となっている。アサフとはダビデの時代に音楽隊の中に出てくる名前(歴代上15章16-24節参照)。 ダビデの時代に生きていたアサフが詩編80編を残したのかもしれない。アサフの詩は、詩編の中に12編ある。2節から8節の詩の内容から、時代背景を想像したい。 上述したように、アサフはダビデの時代に生きていた。 ダビデの功績のひとつは、南北イスラエルの統一とよく言われる。イスラエルの民が、南のユダ国と、北のイスラエル国にわかれていたが、それが統一されていったという。 3節には、「エフライム、ベニヤミン、マナセの前に」とあり、これらは、北のイスラエル国に属する部族である。7節の言葉を読むと、「わたしたちは近隣の民のいさかいの的とされ」ということが書かれており、南北間で別れていたばかりではなく、同じ北イスラエルに属していた、エフライム、ベニヤミン、マナセのそれぞれの部族が、近隣の民の間で、対立しあっていたことも想像できる。アサフは、ダビデの指導力が発揮される前の時代から、部族間のいさかいも、また南北統一に向けても、信仰深く、神の力を信じ、顕現してください(2節)、来てください(3節)、御顔の光を輝かせ、わたしたちをお救いください(4、8節)と祈って、この詩編を歌ったのだろう。
さて、この詩編80編1-8節を通して、主なる神は21世紀を生きている私たちに、今日何を語っているだろうか? 私は、待降節にあって、「顕現してください。」「来てください。」と祈るこの詩編はとても、キリスト教の暦のなかで、ふさわしいと、もちろん思う。 そして、神はお考えがあって、この詩編を現代を生きる民に、しっかり読み、詠い、祈るように導いておられるのだと思う。 現代を振り返ると、この地球上で、さまざまな争いが起こってしまっているのは、多くのメディアが伝えるとおり。 中東で、東南アジアで、アフリカで、ヨーロッパで、またアメリカでも、戦争にしろ、テロにしろ、あるいは家族内でのさまざまないざこざにしても。 このような時代に、落ち着いて、「顕現してください。」「来てください。」と主の到来を祈る、いろいろな意味で、私たち人類が壊してしまっている、この地球上の混沌とした破壊的ともいえるような状況から、この人類を救いだしてください。と祈ることが大切なのだろう。 その信仰が、すべての源にあるのではないだろうか? クリスマスの意味をしっかり覚える時となりますように!
安達均
今年のアドベント、待降節は、第二週から第三週に向かいつつある。駆け足で過ぎていくような感じがする。日本語で十二月は「師走」と言い、普段は落ち着いている師匠すらも走るという季節なのかと思う。 しかし、この時期、立ち止まって、しっかり、御言葉に聴き入る時間を持つことをお勧めしたい。 今週も聖書日課では、通常は詩編を読むところで、詩編ではない箇所が読まれる。今週はイザヤ書が与えられた。12章を読むが、たった6節だけの短い章。 いつもの詩編を読むように、このイザヤ書12章でも、気になる、あるいはインパクトのある言葉や節を挙げる。次に、イザヤが預言した時の気持ちになってどのようなことを語っているか、よく考える。そして神はこのイザヤ12章を通して今日私たちに何を語りかけているか思いを巡らせたい。
1:その日には、あなたは言うであろう。「主よ、わたしはあなたに感謝します。あなたはわたしに向かって怒りを燃やされたが/その怒りを翻し、わたしを慰められたからです。
2:見よ、わたしを救われる神。わたしは信頼して、恐れない。主こそわたしの力、わたしの歌/わたしの救いとなってくださった。」
3:あなたたちは喜びのうちに/救いの泉から水を汲む。
4:その日には、あなたたちは言うであろう。「主に感謝し、御名を呼べ。諸国の民に御業を示し/気高い御名を告げ知らせよ。
5:主にほめ歌をうたえ。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。
6:シオンに住む者よ/叫び声をあげ、喜び歌え。イスラエルの聖なる方は/あなたたちのただ中にいます大いなる方。」
気になる言葉やインパクトのある節はどこだろう? 私にとって、インパクトがある言葉は、1節と4節にある「その日には」という言葉。
預言者イザヤの気持ちを覚えつつ何を語っているか読んでいきたい。イザヤ書は66章からなり、一人のイザヤという預言者だけではなく、複数の預言者によって記されたと思われる。 66章のうち、最初の39章は第一イザヤと呼ばれ、神に背を向けてしまう紀元前8世紀ごろの指導者や民に向けて、辛口の預言がなされている。 そこには、人間の傲慢、神ではない人間の高ぶりが、大きなテーマとなっている。 しかし、「その日には」という言葉ではじまる12章では、そのようなイスラエルの民に、大きな変革の時代が来ることを、イザヤは預言している。1-2節では、イスラエルの民は、神は救い主であることがわかり、その神に感謝する時代が来ることを語る(1-2節)。 そして、枯渇した、いわば瀕死と思われるような状況に陥った民が、喜びのうちに救いの泉から水を汲むことができるようになると述べる(3節)。さらに、イスラエルの民は、その神を賛美し、世界の民に、神の救いを述べ伝えるようになる(4-6節)。
さて、このイザヤ12章を通して、主なる神は21世紀を生きている私たちに、今日何を語っているだろうか? 1節、4節にある「その日には」というその日とはいつのことを言っているのだろうか? 私は、紀元前から紀元後になる、イエスキリストの誕生以降の時代のことを言っているのだと思う。 一人の人間の誕生が、それは救い主の誕生だったが、2000年経っても、祝われ続けている。 それも、イスラエルからはじまって、西にも東にも、救い主降誕の知らせはひろまった。 さらに南半球にも、ひろまっていって、世界中で救い主降誕を祝う時代になっている。 人々は、神とは救い主、イエスであったことに気がつき、喜んでほめ歌を歌い、そして、さらに救い主がこの世に顕われたことを告げ続けている。 クリスマスである。 しかし、現実には、クリスマスを祝う人々は、世界中にひろまり、クリスチャンは25億人と言われても、とてもイエスキリストが救い主だとは信じられない人々、45 億人が世界中にいる。またとくに日本語を話す人々の中では、イエスを神と信じられる人の割合は圧倒的に少ない。主イエスの体である教会に集い、そのイエスの体の一部となっている一人一人のキリスト教徒が、全世界の民に、聖書の御言葉を伝え、クリスマスキャロルを歌い、主イエスの御業・主の憐れみと愛を、示し続けるように、このイザヤ12章を介して、神は導いておられると思う。 アーメン
安達均
アドベント、待降節、にはいり、最初の週の後半は、通常の聖書日課であれば詩編を読むところに、ルカ1章68節から79節が与えられている。 イエスの従兄ともいえるヨハネが誕生した時、その父がザカリアが賛美、預言した箇所だ。 旧約聖書の詩編ではないが、とても意味のある賛歌であり、預言である。 アドベントにあって、じっくり味わっていただければと思う。
68: 「ほめたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、
69:我らのために救いの角を、/僕ダビデの家から起こされた。
70:昔から聖なる預言者たちの口を通して/語られたとおりに。
71:それは、我らの敵、/すべて我らを憎む者の手からの救い。
72:主は我らの先祖を憐れみ、/その聖なる契約を覚えていてくださる。
73:これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは、
74:敵の手から救われ、/恐れなく主に仕える、
75:生涯、主の御前に清く正しく。
76:幼子よ、お前はいと高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、
77:主の民に罪の赦しによる救いを/知らせるからである。
78:これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、/高い所からあけぼのの光が我らを訪れ、
79:暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、/我らの歩みを平和の道に導く。」
ルカ 21:25-36
主の慈しみと平安が会衆の心に与えられますように!
1991年の10月に次男が生まれ、Kanという名前をつけた。 偶然だったが、その年の終わり、レコード大賞は、Kanという名前の歌手がとった。 何という曲だったか覚えているだろうか?
そう、今日の説教タイトル「愛は勝つ」。91年の大晦日に、レコード大賞のテレビ放送を見ていて、「信じることさ、必ず最後に愛は勝つ」とくりかえされるこの曲が歌っていることが、聖書のイエスのメッセージと同じだなと思った。
そして、レコード大賞をとってから25年たっているが、この曲はくりかえしくりかえし、日本では流れているようだ。 2011年にYoutubeにアップされたものは180万回もアクセスされている。
教会暦では新しい年で、福音書としてはルカ福音書が中心でたまに、ヨハネ福音書が読まれる年となった。 そしてその第一日目の聖日は、ルカ21章は、先々週とりあげられたマルコ13章とくりかえしのような部分。信仰者として生きる間に、良い箇所、重要な箇所は、箇所は、くりかえされるのだと思う。
さきほど読んだ聖書の箇所には、「地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民は、なすすべを知らず、不安に陥る。 人々は、この世界に何が起こるのかとおびえ、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。」 というなんとも不気味な言葉がある。
しかし、イエスの言葉は、決して人々を怖がらせることが目的ではない。 今日の箇所は、人々が不安に陥って、あるいは何もできなくなってしまうようなことがあっても、そのような束縛から解放されるという、希望と愛に満ちているメッセージがあるのだと思う。
それは、イエスが「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない。」と言われていることに、世の人々に希望を与えるメッセージがある。 わたしの言葉とは、イエス自身のことであり、またイエスご自身が神の子であり、神は愛に満ちた方。 ヨハネの手紙では、「神は愛である」と書いている。
「決して滅びない」とは、決して負けないということ。 必ず勝つという言い方もできる。 ヨハネ14章から16章には、イエスが十字架にかかる前の晩に話された、長い講和が載っているが、その最後の言葉で、イエスが「私はすでに世に勝っている。」と話されている。
冒頭に話した、「愛は勝つ」を歌っていたKanさんは、小さいころ教会に通っていて、讃美歌をよくうたっていたそうだ。 私が、この曲が、聖書のイエスのメッセージと同じであるということ、わかっていただけるだろうか。
しかし、今日のメッセージは、一歌謡曲が、聖書のメッセージと同じだということだけを伝えたいのではない。第一アドベントに与えられた「愛は勝つ」というこの言葉が、みなさんにどう影響するかということを申し上げたい。
実は、この世の中、また世に生きる一人、一人が、イエスのいわれる通り、現代においても、さまざまな不安に陥って、束縛されてしまう現実がある。 どういうことに束縛されているだろうか? ご承知のとおり、世界中のどこでテロが起こってもおかしくない時代、そして、各国が持つ核軍事力により、いつかは、この世が滅びるのではないかという不安に縛られている方もいる。
あるいは、個人的には、いつか訪れる、自分の死に恐れている方もいる。 あるいは、「学校に行くのが怖くてしょうがない、不登校になってしまった。」 そういう本人、また、そのようなお子さんを抱える、おや、あるいはおじいちゃんおばあちゃんもいると思う。 それゆえに、家庭が束縛されてしまっている家族もいることだろう。
しかし、神の愛は、そのような中に、いっしょになって、入ってきてくださっている。 自分はその愛を受け取るだけでいい。 それさえあれば、神が私たちの束縛から解放してくださる。
「愛は勝つ」のYoutubeの書き込みに、以下のような事を書いていた”Harukana”というニックネームの方がいて、紹介したい。 「小学生の時、不登校児だった私。先生が迎えに来てくれた車の中で先生はずっとこれを流していた。 一年生だったから全然意味わからなかったけど、あれから数十年、、、その時の先生と同じ年になりました。なぜか先生といわれる仕事につきました。子どもも生まれて小学生だけどなんと私と同じ道をたどっています。 今なら先生の気持ちが痛いほどわかります。 先生あの時はごめんなさい。そしてありがとうございました。今度は私が子どもに伝えていきます。」
どのような時代が来ようが、そのような家庭生活となろうが、どのような人生であろうが、どのような困難を受けているかもしれない。 しかし、今日あるいは、少なくともこの待降節の間に、それらから逃れて、すべてに勝つことができる神の愛に向き合う道を永遠に歩めますように。 アーメン
安達均
“Love Wins”
Luke 21:25-36
May the Grace and Peace of the Lord be poured into the people’s hearts in this sanctuary!
In October 1991, our second son, Kan was born. Coincidently, in 1991, a singer-songwriter with the same first name Kan received the Japan Record Award called “Record Taisho”. Does anyone remember the name of the song?
Yes, the tile of the song is the same as today’s sermon title, “Ai wa Katsu” which means “Love Wins.” When I was listening to the song in the New Year’s Eve of 1991, I thought that the meaning of the song is really the same as what Jesus said as written in the Bible.
Even 25 years after the song was awarded “Record Taisho”, this song is often heard in public. I checked YouTube and found that a video of the song, posted 2011, was accessed 1.8 million times.
Well, let’s talk about the Gospel text today. Today is the first Advent Sunday. The new year just started in our Church Calendar. This year, on Sundays, Luke (or John several times) will be read as Gospel. However the content will often be the same text as Mark or Matthew. Actually, the text today is again very similar to what we read two weeks ago in Mark 13. The good and important message is read again and again during our Christian lives.
In the text I just read, there were these words, “on the earth distress among nations confused by the roaring of the sea and the waves. People will faint from fear and foreboding of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken.” It is an eerie passage.
However, the purpose of Jesus’ words is not causing people fear but rather freeing them from fear or from the bondage of being in distress and being unable to act. I believe the Jesus’ message is filled with his hope and his everlasting love.
Jesus said, “Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.” In His Word, there is his promise of love. “My word” itself means, Jesus himself, and Jesus is the Lord, our God. And God is love as John said in his first letter in Chapter 4.
“Not pass away” can be translated to “not lose” or “win.” In John’s chapter 14 through 16, there is a long discourse detailing what Jesus said in the evening before he was crucified. At the end of his discourse, he said, “I have overcome the world.”
Kan, the singer-songwriter, who wrote “Ai wa Katsu: Love Wins” went to church when he was small and often sang hymns. Hopefully you understand why I said that the meaning of the song and the Jesus’ message are the same.
However, today’s message is not really about understanding that a popular Japanese song and the message of the Bible are the same. Rather, I would like to proclaim how “Ai wa Katsu, or Love Wins” affects us and affects the world.
In reality of our lives, we often become distressed. The world often becomes bound by fear. What kind of bondage do we feel ln our lives now? What is restricting the world from becoming a calm and peaceful place? What is restricting us from being freed from fear? As has been reported there have been several, recent incidents of terrorism. Some may feel that the world will end in nuclear war(s). Or some may fear their own earthly death. Or some might worry so much about their child or children’s education and their future they cannot do other things as effectively…
However, the good news is God’s love is coming into our world and given to all people in this world. Jesus frees us from any kind of earthly bondage. The only thing we have to do is just accept his Love, God’s Word that was proclaimed by Jesus. His love was and is and will be within us and among us forever. Whatever happens in this world, God’s word will never pass away, and because of this Jesus wins and His Love wins.
Someone named “Harukana” meaning “Far Away” posted about her life on the “Ai wa Katsu: Love Wins” YouTube site in Japanese. I would like to share what she wrote: “When I was an elementary student, I could not go to school. My first grade teacher had picked me up so I could go to school without being afraid. In that car, my teacher was playing this song, “Ai wa Katsu: Love Wins” again and again. Since I was only in the first grade, I did not understand the meaning. Since then, more than a few decades have passed. Now I am my first grade teacher’s age. For some reason I too became a teacher. Now I have a child and she is following the same path as me. Now I painfully understand how you, the teacher, felt about me. I am very sorry that I didn’t fully understand at that time and I thank you. Now, I’m imparting the same teaching to my child.”
Whatever the world may become, whatever life path we are walking, whenever it seems difficult, today or at some time during this advent season, as we await the Birth of Jesus Christ and his second coming, I pray that we are freed from any bondage and notice that we are walking with Jesus’ Love and that it overcomes everything. Amen.
Pr. H. Adachi
2015年11月22日LCR日本語部週報通算第1378号
November 29, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
11月26日、木曜は、11月の第四木曜日で感謝祭。 そして、教会の暦では、新しい年を迎えた。今週木曜日から、新しい年の最初の聖日(降誕節第一主日)まで与えられている詩編は25編の1-10節。 気になる、あるいはインパクトのある言葉や節を挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編25編を通して今日私たちに何を語りかけているか思いを巡らせたい。
詩編25編
1:【ダビデの詩。】主よ、わたしの魂はあなたを仰ぎ望み
2:わたしの神よ、あなたに依り頼みます。どうか、わたしが恥を受けることのないように/敵が誇ることのないようにしてください。
3:あなたに望みをおく者はだれも/決して恥を受けることはありません。いたずらに人を欺く者が恥を受けるのです。
4:主よ、あなたの道をわたしに示し/あなたに従う道を教えてください。
5:あなたのまことにわたしを導いてください。教えてください/あなたはわたしを救ってくださる神。絶えることなくあなたに望みをおいています。
6:主よ思い起こしてください/あなたのとこしえの憐れみと慈しみを。
7:わたしの若いときの罪と背きは思い起こさず/慈しみ深く、御恵みのために/主よ、わたしを御心に留めてください。
8:主は恵み深く正しくいまし/罪人に道を示してくださいます。
9:裁きをして貧しい人を導き/主の道を貧しい人に教えてくださいます。
10:その契約と定めを守る人にとって/主の道はすべて、慈しみとまこと。
気になる言葉やインパクトのある節はどこだろう? 4節にある「あなたの道をわたしに示し/あなたに従う道を教えてください。」
詩編作者の気持ちを覚えつつ1節づつ読んでいきたい。1節に【ダビデの詩。】となっており、詩編作者は、特に2節後半の言葉から、ダビデが敵に囲まれ危機的状況にあった時のことを想像しながら、この詩を詠ったのかと思う。この詩編の言葉は、1)神との信頼を宣言する箇所、2)神への要望を述べる箇所、3)詩編作者が教訓を述べる箇所のどれかに属する言葉が並べられて構成されているようだ。そこで、そのどれに属するかを考えつつ、一節づつ振り返りたい。 私の魂はあなたに望みを置いています、神よ、あなたを信頼してお願いします(1節と2節前半:信頼)。私が恥を受けることがないように、また敵が誇ることのないようにしてください(2節:要望)。あなたに望みを置くものは恥を受けることがなく、人を欺く者が恥を受ける(3節:教訓)。主よあなたの道を示して、あなたに従う道を教えてください、あなたの真理に私を導いてください(4節、5節前半:要望)。あなたは私の救いの神で、あなたに永遠の望みをおいています(5節後半:信頼)。主よ、あなたの永遠なる憐れみと慈しみを思いだしてください、わたしの若き日の罪や背きを思い出すことなく、主の慈しみと恵みの中に私を留めてください(6-7節:要望)。主は恵み深くて正しく、罪人にも道を示してくださる、主は謙(へりくだ)る者を認め、主の道を教えてくださる、約束を守る者にとって、主の道は慈しみと真理である(8-10節:教訓)。
教会暦で新年度に入る中、また感謝祭の時に、この詩編を通して、神は私たちに、次の三点を授けているように思う。1)しっかり神との信頼の中で、新しい年も神の招きに応じて礼拝に仕える。2)過去の起こった様々なことから教訓を思い出し、神の恵みを数える。3)新しい年を迎えるにあたって、私たちの歩む道が、主の御心にかなった進路になるように祈る。