2015年7月12日LCR日本語部週報通算第1350号
July 12, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
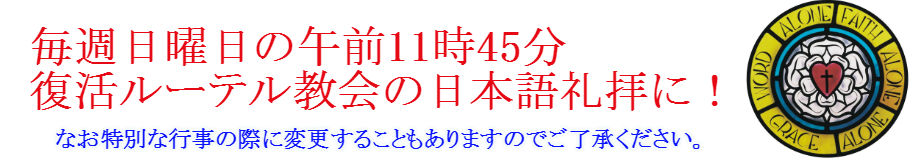
2015年7月12日LCR日本語部週報通算第1350号
July 12, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週は7月9日から12日の聖書日課に与えられている詩編85編9節からを読もう。とても短い箇所を読むが、第二次世界大戦の終了から70周年を迎える年にあって、含蓄のある言葉が多く含まれている。いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編箇所を通して現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編85編
9: わたしは神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます/御自分の民に、主の慈しみに生きる人々に/彼らが愚かなふるまいに戻らないように。
10:主を畏れる人に救いは近く/栄光はわたしたちの地にとどまるでしょう。
11:慈しみとまことは出会い/正義と平和は口づけし
12:まことは地から萌えいで/正義は天から注がれます。
13:主は必ず良いものをお与えになり/わたしたちの地は実りをもたらします。
14:正義は御前を行き/主の進まれる道を備えます。
気になる言葉としては、「主は平和を宣言されます」という言葉。
詩編作者の気持ちになって、一節づつ、読んでいきたい。 主なる神が、平和を宣言・約束される、それは、主の慈しみに希望をおいて生きる人々に昔のような神に背く行いをしないようにするため(9節)。 主を畏れる人にこそ、救いは近く、神の栄光は、その主を畏れる私たちの生きる地に留まるでしょう (10節) ――栄光が地に留まるという、栄光が人格化されていることに注目。神の慈しみは人々の地上のまこと(ヘブライ語ではwe-e-metという言葉が使われており信仰深いという意味もある)と出会い、また神の正義は人々の間に存在する平和と口づけする――さらに神の”慈しみ”と”正義”も人格化されていることに注目(11節)。 人々のまこと(信仰)は植物が地上から芽を吹いて成長するかのように天に向かって萌え出でて、神の正義は天から雨が降るかのごとく地に注がれる(12節)。 主はかならず良いものを地に与え、私たちの地に実りがもたらされる(13節)。 神の正義が主の前を先行し、主の歩む道を整える(14節)。
さて、この詩編85編の後半部分を通して、主なる神は、現代に生きる私たちに何を語りかけているのだろうか? 私は、栄光・慈しみ・正義―――これらは神に供えられているのだと思って、上記では、わざわざ「神の」という言葉をつけて表現したが、紀元数百年前にすでに、「地に留まる」「まことと出会う」「平和に口づけする」などの動詞から、人格化されて詩編に詠われていたことに驚かされる。そして、神はイエスという人において、顕われてくださったことと、結びつき、そして、現代においても、聖霊という神の存在が、人格化されてこの世に生きていることにも、通じているのだと思う。また現代に生きる人類が抱く信仰(上記に書いたように「まこと」と訳されているヘブライ語は信仰に置き換えることもできる)は、植物が成長するように、この地から天に向かって伸びていくかのごとく成長していく様子を思い浮かべる。植物が天からの雨が注がれて育っていくかのごとく、地上の人々が抱く信仰も、天から良い恵みを注がれて、どんどん成長していくことが、現代においてもおこりうることを覚える。 そして、そのような民は、神の意志に背いて戦争をしてしまうような振る舞いに戻るようなことをしないようにしてくださり、聖霊なる神は平和を宣言してくださる。第二次世界大戦終了から70年が経つ年にあって、まさに主の平和の宣言が、いまこそ、起こりうるのだと思う。 平和には、人々の信仰が鍵なのかと思う。
アーメン
安達均
今週は7月2日から5日の聖書日課に与えられている詩編123編を読もう。とても短い詩編だが、120編から134編は、すべて最初に「都に上る歌」との説明書きがあるので、120編から134編が一つの大きなグループの詩編で、その一部が123編ともいえる。 いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編箇所を通して現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編123編
1:【都に上る歌。】目を上げて、わたしはあなたを仰ぎます/天にいます方よ。
2:御覧ください、僕が主人の手に目を注ぎ/はしためが女主人の手に目を注ぐように/わたしたちは、神に、わたしたちの主に目を注ぎ/憐れみを待ちます。
3:わたしたちを憐れんでください。主よ、わたしたちを憐れんでください。わたしたちはあまりにも恥に飽かされています。
4:平然と生きる者らの嘲笑に/傲然と生きる者らの侮りに/わたしたちの魂はあ まりにも飽かされています。
気になる言葉としては、「飽かされています」という、あまりピントこない言葉。 前後関係から理解して、また辞書でも調べてみたが、「満ちている。」とか「十分にある」という意味なのかと思う。
さて、詩編作者の気持ちを想像しながら、短い詩編をじっくり振り返りたい。 冒頭にも書いたように、詩編120編から、都に上る歌がはじまっている。 エルサレムから遠く離れた所から、三日位かかって、エルサレムに上ってきたような感じがする。 毎日一編づつ、詩編を詠いながら。 そして、エルサレムの神殿をまん前にして、この詩編123編を詠っているような、信仰深い詩編作者とその一族の様子が思い浮かぶ。 目をあげて、わたしは(一族の長)が主を仰ぎみます、天におられる主よ、と呼びかける(1 節)。 僕(しもべ)が主人の手を見守るように、また女奴隷が、その女主人の手を見守るように、私たちは、今、主なる神を見守り、憐れみを待ちます(2節)。1 節が家長の個人的な神への呼びかけ、2節は家族・共同体としての神への呼びかけが大きなテーマで、神の憐れみを願う。3-4節では、2節に引き続き、憐れみの祈願が繰り返され、そして、なぜそんなに憐れみを願うのかを説明すべく、共同体が背負っている心の重荷の告白になってくる。 どうか私たちを憐れんでください、主よ、憐れんでください、わたしたちの心はあまりに、恥に満ちています(3節)。 私たちの魂は、世の中を、ただ思いわずらいもなく生きている者たちからの嘲りに、また私たちを見下して生きる者たちからの侮辱に、あふれています(4節)。 そこには絶対的な神に頼って信仰をもって生活する詩編作者やその家族が、周辺の人々からは、ばかにされ侮られてきた様子が思い浮かぶ。 そして、耐え切れずに、エルサレムに上ってきて、神殿で、主に憐れみを請う姿が現れている。
詩編123編を通して、神は何を現代の私たちに語ろうしているのか? 詩編が記された紀元前数百年前から現代の話に飛んでしまう前に、イエスキリストの時代のことを思い返したい。 7月5日の聖日に与えられている福音書は、マルコ6章1-13節になるが、その前半部分では、イエスが生まれ故郷のナザレでは、ほとんど相手にされないというか敬われない様子が描かれていた。 そして、現代の教会の指導者たちも、自分の生まれ故郷では、周囲の人々から侮られてしまうということは起こっているのではないかと思う。 また、指導者ばかりではなく、現代においてキリスト信仰に生きる者は、社会からは嘲笑、侮辱の対象になってしまうことも否定できない面がある。そこには、信仰者が一人で社会に存在しているだけでは、とてもやりきれなくなってしまう面があるのではないだろうか。 だからこそ、詩編作者とその群れが、エルサレムの神殿に向かったように、現代の信仰者も、週一回は、謙って主を賛美しつつ、礼拝堂に集い、自分たちの重荷を告白して主の憐れみを請い、恵みの御言葉を聞き、新たに主に頼る信仰を強め、恵みに応答して捧げ、聖餐に授かって、また世の中に派遣されていく、そのような生活に導かれているように思う。
アーメン
安達均
マルコ5:21-43
主イエスの恵みと平安が豊かに与えられるように!
6月3日から8日まで、結婚30年ということもあり、妻と私は休暇をいただきボストンを旅行した。 休暇といっても、やはり日曜朝どこで礼拝を捧げるか、教会を探した。 4日の木曜の朝、場所を確認するため最初の候補だったハーバード大学近くにある、University Lutheran Churchに出向いた。
すると今年第二次世界大戦終了から70年にあたり、世界ではじめて原爆投下となってしまった日本時間8月6日午前8時16分、東海岸時間で8月5日午後7時15分に向けて、5月28日から、毎晩7時から7時15分まで、70日間の祈り会が持たれているという張り紙を見つけた。
広島の原爆というと、いろいろなことを思い浮かべる。 私は、今日ここで、原爆が良かったとか悪かったとかを話すつもりは毛頭ない。 ただ、2歳で被爆して、12歳で白血病で亡くなった佐々木貞子さんの話をしたい。
彼女はそれまで育ててくれた両親、家族、友人たちとの別れが来ることはわかっていた。しかし、語り継がれた話を信じて、希望を決して捨てなかった。折り紙で千羽鶴を折れば、翼が与えられ、飛ぶことができ、永遠の命が与えられると。
本日与えられた福音書では、メッセンジャーから会堂長とイエス、そして弟子たちに、12歳の娘がもう亡くなったというニュースが届く。 もう亡くなったのだから、イエスにわざわざ来てもらうことは無いとまで言われてしまう。
しかし、イエスと会堂長、イエスの弟子たちは、急いで、会堂長の家に出向く。 そして、イエスは会堂長に、「恐れることはない、信仰を持ちなさい。」 と語っていた。
ここで、イエスの言う「信仰」とは何だろか。 先ほど読んだ福音書の中で、出血の止まらない女性が、この人に触れば救われると思い、必死でイエスに触ろうとする様子が描写されていた。そこに、真の信仰が著されていたように思う。
イエスは、「あなたの信仰があなたを救った」と言われる。 信仰とは、あきらめや不安を乗り越えて、絶対なる神に信頼を置く事と言える。 信仰は信じることだが、信じるという頭の中の働きだけではなく、信仰の結果として行動に顕われると思う。
そして、イエスは、娘が亡くなり、近隣の者たちが泣き騒いでいるなか、娘の両親と3人の弟子だけを連れて、娘のいるところに入っていく。 神から絶大な信頼を受けたイエスが、「タリタ クミ」、「少女よ立ち上がりなさい」というと、確かに12歳の少女は立ち上がって歩き出す。 それはイエスだけが奇跡を起こしたわけではなく、父親、母親、さらには3人の弟子たちの信仰もあって、奇跡が起こった。
くしくも同じ12歳だった佐々木貞子、私が調べた限り、彼女がクリスチャンになっただとか、キリスト教の神を信じたという記録は何もない。 しかし、私には、彼女の思い、祈り、彼女の信仰は、絶対なる神、この世の救い主、イエスに届いていたと思う。
そして、神はそれに答え、「タリタクミ」という言葉をなげかけ、折鶴を折り、祈り続けた彼女は世界中を羽ばたいているように思えてならない。 佐々木貞子は、世界中の人々の心に、生きているのだと思う。 西海岸だけでも、少なくともシアトルとサンタバーバラに佐々木貞子の碑が立てられている。
さて、今、あまりにも、多くの戦いが起こっている現実がある。 国家レベルの戦争もあれば、テロリストとの戦い、また、先週は本当に言葉に言い表しようのない教会での銃撃事件が起こってしまった。
繰り返し起こる銃撃事件、繰り返されるテロ、繰り返される戦争を現実に見る中で、私たちは、主イエスから「立ち上がりなさい」と呼びかけられていることを感じる。 私たちは、あきらめることなく、不安を乗り越えて、主なる神、主イエスキリストに絶対的な信頼を置き、祈り願う。 真の信仰が求められているのではないだろうか。
University Lutheran Church での70日間の祈りの行動に感化され、カール牧師と教会のスタッフで、”40 Days of Peace”という小冊子を用意した。今年の終戦記念日を迎える前、40日間、さまざまな困難にある社会また、世界平和に向け、祈り考えていきたい。 7月7日にはじめれば終戦記念日の8月15日に終了する。
8月16日の日曜日の平和主日礼拝では、主イエスから平和を実現する人々となるように呼びかけられていることを覚え、礼拝の時を持ちたい。 祈りをもって、今日のメッセージを終了したい。
慈しみ深い神よ。 さまざまな問題をかかえる社会状況のなかで、主に祈ります。 どうか、ひたむきな信仰を持つことができますよに!
アーメン 安達均
“Talitha Koum, Little Girl, Get Up!”
Mark 5:35-42
May the Lord’s Grace and Peace be poured into the hearts of the people gathered in this sanctuary!
In early June, Satoko and I took a vacation to Boston for our 30th anniversary. Even though we were on vacation, we still looked for a place to worship on Sunday June 7th. At first, we chose University Lutheran Church near Harvard University.
On Thursday morning, my wife and I were walking there to verify its location. While walking, we found a poster saying that they pray for peace every night from May 28th through August 5th between 7:00 p.m. and 7:16 p.m. Since this year is the 70th anniversary of the end of World War II, they decided to pray for 70 days from May 28th until 7:16 p.m. Eastern time on August 5th which is the time when the first Atomic Bomb was dropped on Hiroshima at 8:15 a.m. (Japan time) on August 6th.
If we think about that incident, various images will come to mind, but I want to make sure that this message doesn’t discuss whether it was right or wrong. Instead, I want to focus on a girl who, at 2 years old, experienced the radioactive effects of the bomb because she was 1 mile away from the ground zero. Because of her exposure, at the age of 12 she passed away due to leukemia. Since some of you went to Hiroshima, you might remember her name, Sadako Sasaki.
She knew that she had to say goodbye to her beloved family and friends, but she never gave up hope. She believed by praying and folding thousands of paper cranes, she would be given wings, fly and live forever. People continue sharing her tragic, but inspiring story to this day.
Here, I would like to dive into the Gospel text. The messengers from Jairus’ family came to Jairus, was a leader of the local synagogue. His 12-year old girl had died. Since she was already dead, people told Jesus it was not worth it for him to visit their family, although Jairus did ask him to come and save her once.
However, Jesus said to Jairus, “Fear not, and have faith,” then Jesus and the three disciples made their way, past people openly mourning and weeping in front of the home, and accompanied Jairus into his home.
Jesus said, “Have faith.” What does this statement mean? What kind of faith does he want Jairus and others to have? Mark told another story before the messenger came to Jesus A woman in the crowd suffered constant bleeding for twelve years. Despite her pain, she did not give up hope and thought that if only she touched Jesus, she would be healed. I think this is the type of faith Jesus wants people to have.
Jesus said, “Daughter, your faith made you well. Go in peace. Your suffering is over” I think faith is not just believing something in one’s mind, but it’s overcoming one’s fear/hopelessness, never giving up and trusting almighty God 100 percent. Action follows sincere faith.
After Jesus felt God’s healing power cure the woman, he then came to the home where Jairus’s dead daughter was, saying to her, “Talith Koum” which means “Little girl, get up.” The 12 year-old girl got up and started walking around her home. Jesus’ faith in God’s power alone did not revive the girl; her parents’ faith was necessary as well.
Let’s return to Sadako Sasaki’s story. I have not seen any articles or records that showed that she was a Christian but I believe her innocent faith and her prayers were/are connected to our God.
Responding to her prayers, God made her spirit fly with thousands of paper cranes and she is living within the hearts of people all over the world. I know of at least two statues honoring Sadako along the West Coast. One’s in Seattle, Washington and the other’s in Santa Barbara, California.
In today’s world, there are different types of conflicts. Two such conflicts are wars fought by nations and domestic struggles such as protesting racial inequality. I am still not sure if any words can adequately express my feelings on the matter. At Mother Emanuel Church in Charleston, South Carolina; despite such an horrific act, I believe God is urging us to have true faith, telling us to never give up hope, to trust and rely on Him 100 percent and to pray for Christ’s peace. God is always with us, but especially during times of great need.
When hope seems dead and the world seems full of violence, God tells us to “Get up” and guides us to serve and glorify him! He knows what we ought to do. As such, why don’t we continue praying for the world?
Inspired by what University Lutheran Church is doing for 70 days, Pastor Carl Zimmermann and church staff prepared “40 Days of Peace” it’s designed for people going through difficult times and also remembering World War II’s end on August 15, 1945. If you start using this inspirational material on July 7th, you will complete 40 days on Saturday August 15th. Then on Sunday, August 16th, our worship services will focus on Christ’s call for us to be peacemakers.
Dear Gracious God, holy and almighty, we pray to you, in this time of conflict. May we have whole-hearted faith, we pray in hour holy name! Amen.
Pr. Hitoshi Adachi
2015年6月28日LCR日本語部週報通算第1358号
July 28, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週は6月29日から7月1日の聖書日課に与えられている詩編88編を読もう。はっきり言って、暗い詩編だ。ここまで暗い詩編はほかにないのではないかと思う。 しかし、神の御心があって、この詩編は加えられているのだと思う。詩編作者の立場にたって、また、21世紀に生きる私たちにとって、その御心はなんなのか、考えたい。いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編箇所を通して現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編88編
1:【歌。賛歌。コラの子の詩。指揮者によって。マハラトに合わせて。レアノト。マスキール。エズラ人ヘマンの詩。】
2:主よ、わたしを救ってくださる神よ/昼は、助けを求めて叫び/夜も、御前におります。
3:わたしの祈りが御もとに届きますように。わたしの声に耳を傾けてください。
4:わたしの魂は苦難を味わい尽くし/命は陰府にのぞんでいます。
5:穴に下る者のうちに数えられ/力を失った者とされ
6:汚れた者と見なされ/死人のうちに放たれて/墓に横たわる者となりました。あなたはこのような者に心を留められません。彼らは御手から切り離されています。
7:あなたは地の底の穴にわたしを置かれます/影に閉ざされた所、暗闇の地に。
8:あなたの憤りがわたしを押さえつけ/あなたの起こす波がわたしを苦しめます。〔セラ
9:あなたはわたしから/親しい者を遠ざけられました。彼らにとってわたしは忌むべき者となりました。わたしは閉じ込められて、出られません。
10:苦悩に目は衰え/来る日も来る日も、主よ、あなたを呼び/あなたに向かって手を広げています。
11:あなたが死者に対して驚くべき御業をなさったり/死霊が起き上がって/あなたに/感謝したりすることがあるでしょうか。〔セラ
12:墓の中であなたの慈しみが/滅びの国であなたのまことが/語られたりするでしょうか。
13:闇の中で驚くべき御業が/忘却の地で恵みの御業が/告げ知らされたりするでしょうか。
14:主よ、わたしはあなたに叫びます。朝ごとに祈りは御前に向かいます。
15:主よ、なぜわたしの魂を突き放し/なぜ御顔をわたしに隠しておられるのですか。
16:わたしは若い時から苦しんで来ました。今は、死を待ちます。あなたの怒りを身に負い、絶えようとしています。
17:あなたの憤りがわたしを圧倒し/あなたを恐れてわたしは滅びます。
18:それは大水のように/絶え間なくわたしの周りに渦巻き/いっせいに襲いかかります。
19:愛する者も友も/あなたはわたしから遠ざけてしまわれました。今、わたしに親しいのは暗闇だけです。
気になる言葉としては、11節から13節に書かれた質問。しいて一つあげるとすれば、「滅びの国であなたのまことが語られたりするのでしょうか。」
詩編作者の気持ちになって、この詩編箇所を振り返りたいが、長いので、三つの箇所にわけて、要点だけ。 1節の詳細説明は避けるが、楽団を形成して、この詩編が歌われる様子が思い浮かぶ。2-10節の内容は、社会から疎外されてしまった詩編作者自身と、ほかにも、疎外されてしまった人々がいて、みな、閉ざされた墓、暗闇の地にいると詠う。しかし、2節の最初は「主よ、私を救ってくださる神よ」との神への問いかけではじまり、10節は「あなたに向かって手を広げている。」との言葉があることから、詩編作者が神に祈り続けており、神への希望を捨てていない状況がわかる。11-13節は、決定的ともいえる質問をしていると思う。死者に神の御業が起こるのか、滅びの国にあなたのまことが語られるのか、等々。これらの質問に対して、答えが明確に書かれているわけではないが、真っ暗闇にいる詩編作者は、「いやそんなことはありえない。」という考えに陥っているのだと思う。14節から19節は、さらに真っ暗闇に入っていく様相で、神からも突き放されてしまうと詠う。そして、「私に親しいのは暗闇だけだ。」という言葉で終わっている。しかし、それでも、詩編作者は、その心境を神に向かって、詠っていることに注意したい。
詩編88編を通して、神は何を現代の私たちに語ろうしているのか? 社会からも疎外され、神からも見放され、墓にいるしかないような自分、あるいは滅びの民のようではあるが、それでも主なる神に語り祈り続けようとする信仰に、とてつもないパワーを感じる。21世紀、教会ですら悲しい銃撃事件がおき、本当に暗い世の中だと感じている人々が多いのが現実なのかと思う。実は、墓にいる死者をも蘇させることができる神に徹底的に祈る信仰が求められている。 安達均
マルコ4:35-41
主イエスの恵みと平安が、ここに集まった会衆の上に、さまざまな理由で礼拝に来られずにいる人々の上にも豊かに注がれますように!
イエス様の目から見れば、このように行動したら良いということはわかるけど、回りの人々の目が気になり、とてもそんなことはできない、と思うことがあるだろうか。
たとえば、この人を教会に誘ったら、こんな人は誘わないで欲しいと言われてしまうのではないかとか。しかし、そういうことは決してあってはない。
さきほど読んだ福音書の内容に入っていくが、どのように聞かれただろうか? イエスさまはすばらしい、どんな怖いことがあっても、だいじょうぶ。イエス様が波を沈めてくださる。台風が来ようが、火山爆発があろうが、地震が来ようがだいじょうぶ、イエス様がなんとかしてくださる。ということなのだろうか。
実は、今日与えられていた聖書箇所は、サウスカロライナ州チャールストンで起こってしまった銃撃事件と多いに関係があるのだと思う。
今日の福音書は、与えられた聖書箇所のイエスの言葉とともに、福音書記者マルコが意図したことや、弟子たちの気持ちも想像してみる必要を感じる。それは、今日の聖書箇所の前後にどんなことが書いてあるかにも気を配って、今日の箇所を考えると良いのだと思う。
今日読んでいるマルコ4章35節以前は、種蒔きをする人のたとえ、灯火や秤のたとえ、からし種とたとえといった、すべてたとえ話で来ていることに注意したい。 一連のイエスのたとえは終わり、イエスが「むこう岸に渡ろう。」と、イエスが語られる言葉ではじまっている。さて向こう岸とはどこだろうか?
それは5章のはじめを読むとわかるのだが、向こう岸でも、さらに内陸に入っていったゲラサ人が住む地域をイエスは目指していた。それは、ユダヤ人ではなく、異邦人の地域。 弟子たちにとっては、文化も違うし、考え方も違っていて、いわば外国だった。
弟子たちにとっては、「なんで、そんなところに行くのですか、イエスよ?」 という気持ちがあってもおかしくない。 弟子たちは、キリストの世界宣教などまだわかっておらず、ユダヤ人のわたしたちだけで、楽しく過ごして、ユダヤ人たちだけが、病気が癒されたり、おなかがすいたときには、おなか一杯食べてれば良いのだ、なんて思っていたのではないだろうか。だからイエスから異邦人の地に行こうという指示に、弟子たちの心は穏やかではなかったのだと思う。
このように読んでいくと、このガリラヤ湖が大荒れで、激しい突風がおこって、船が水浸しになってしまう光景は、いわば、弟子たちの心を表す、たとえのようにも思えてくる。 イエスは、「黙れ、静まれ」と風に向かって叱られる。その様子は、弟子たちが、「私たちのよく知らない異邦人の町なんかにいくのはやめましょうよ」と言いたくなるような、おだやかでない弟子たちの心境に対して、自分よがりの文化に、叱っているのではないだろうか。
そして、今日の福音書箇所の最後のイエスの言葉は、「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか。」と言われている。 これから文化や方言も異なり、また悪霊にとりつかれてしまっている人々に解放をもたらする異邦人伝道に対し、イエスは弟子たちに私を信じて、勇気を持ってついてきて、いっしょに宣教の業に励むように導いているのではないだろうか。
今日の福音書箇所は、チャールストンでの銃撃事件で、大きな動揺を覚えるアメリカ福音ルーテル教会の牧師や信徒たち、またどこの宗派であろうが、バイブルスタディの真っ最中であのような事件がおこって心境おだやかではないキリスト者の心境を、嵐にたとえて語っているように思えてくる。
事件のおこったマザーエマニュエル教会でアフリカ系アメリカ人の方々9人が亡くなったが、二人の牧師は、サウスカロライナ、コロンビアにあるルーテル神学大学で学んだ方たちだった。さらに残念に思うのは、銃撃犯の21歳のデュランルーフは、アメリカ福音ルーテル教会のヨーロッパ系アメリカ人の会員だった。
イエスキリストの伝道ということを考える時、いろいろ悩むことがある私たちである。キリストの教えはすばらしいのだが、キリスト教といえども宗教であり、社会では、「宗教は友達を失くすのよ。」なんていわれたりしてしまう。伝道することが恐ろしくなってしまう私たちの存在がある。
そのような社会に、イエスは「黙れ、静まれ」と言ってくださる。そして異なる文化、考え方の方々の中に入っていき、対話するように導いているのだはないだろうか。
あのような事件が起こる現代の世の中にあって、そこに躊躇がある私たちに、「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか。」という言葉を、新たに投げかけてくださり、私たちは、祈り、常に隣につきそってくださっている主イエスを覚えて、今週も主に従う生活を歩もう。
(日本語説教は、サウスカロライナの銃撃事件により、当日礼拝の直前に、内容をかなり追加・削除した。下記英語訳は、追加・削除前のものであること、了承いただきたい。)
アーメン
安達均
“Why Are You Afraid? Do You Still Have No Faith?”
Mark 4: 35-41
May the Grace and Peace of Jesus Christ be poured into the hearts of the people in this sanctuary!
There are times, when we know this is God’s will and we act without hesitation. However, there are times when people around us may not agree it’s the correct action and we are unable to act decisively.
For example, if I invite this person, I might be taken advantage of. Regardless, all are welcome to church, this is our calling. And consequently, all people are invited to welcome others to church, too.
Let’s talk about the Gospel text. What did you learn about Jesus? Jesus is powerful; he calms you when you’re fearful. He even calms stormy weather.
I believe we should focus on Mark’s intentions and the disciples’ feelings about what occurred. It is almost always helpful to read what was written before Scripture and after Scripture to better give context.
Before the scripture, Chapter 4 is all about parables. Parables of the scattering seed, parable of the lamp, and mustard seed. At the end of Chapter 4, in today’s Gospel, Jesus began with the words, “Let’s cross to the other side of the lake.” What is on the other side of the lake?
If you read Chapter 5, you will know what’s there. Jesus was heading not only to the seashore, or I should I say lakeshore, but he was headed much farther inland to a place called “Gerase.” The people that lived there were called Gerasenes. Obviously, they were not Jews. So for his Jewish disciples, the other people were Gentiles and their cultures and languages were different from theirs.
His disciples might have said, “Oh Lord, why are we going to such a place?” Most likely, they did not yet understand what Jesus was envisioning for worldwide evangelism. For disciples, they were maybe thinking about having fun and eating together only among Jews in other Jewish communities. They also, most likely, believed only Jews would be healed from diseases and freed from bondage.
Reading the scripture this way, we might say that the strong storm, the strong waves, and the swamped boat are metaphors of the disciples’ hearts. The storm, waves, and the boat, in the scene described in Scripture itself may be the parable of the disciples’ feelings about how they did not want to go further into Gentile land across the Galere.
They wanted to say, “Let’s not go across to the other side.” Jesus said to the wind “Peace! Be Still!” and it was also said to the disciples’ hearts who were uncomfortable and uneasy about going across the lake.
In today’s text Jesus’ last words are, “Why are you afraid? Have you still no faith?” To his disciples these words meant, “Fear not, let’s proclaim the good news of Jesus to the Gentiles, heal the sick, cast out demons, and free the Gentiles from bondage.” “Why don’t you have enough faith in me to spread God’s word to people in surrounding communities and beyond?”
For us living in the 21st century, the scene described in the Gospel may be a parable of our situation. When we think about the mission of Jesus in this world now, we sometimes wonder if we should proclaim the peace of Christ. Even though we think that Jesus is wonderful, Christianity is still a religion that the world dislikes or misunderstands in general. In Japanese community, especially, we hear “Religion causes you to lose your friends.” Because of misconceptions like these, we sometimes fear talking to others about Christ.
Don’t you feel that Jesus is telling this world “Peace! Be Still!” Jesus is asking us now “Why are you afraid? Do you still have no faith?”
Confucius said, “A person of virtue is not isolated. He must have some companions.” This was told almost 5 centuries before Christ, but for me as someone who is alive after Christ’s ascension, I say, “A person who shows Jesus’ love is not isolated, instead he always has a companion, humanity’s friend, Jesus our Savior and Lord.”
Today, we are hearing Jesus “Why are you afraid? Do you still have no faith?” in a new way. When we act in the will of Jesus, our companion, our friend, Jesus Christ is always with us.” During this new week, let’s act as Jesus wants us to act. We live to serve God; He is with us! Fear not, if the world disagrees.
Amen.
Pr. Hitoshi Adachi
2015年6月21日LCR日本語部週報通算第1357号
June 21, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週は6月18日から21日の聖書日課に与えられている詩編107編1-3節および23-32節を読もう。いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編箇所を通して現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編 107編
1:「恵み深い主に感謝せよ/慈しみはとこしえに」と
2:主に贖われた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らを贖い
3:国々の中から集めてくださった/東から西から、北から南から。
23:彼らは、海に船を出し/大海を渡って商う者となった。
24:彼らは深い淵で主の御業を/驚くべき御業を見た。
25:主は仰せによって嵐を起こし/波を高くされたので
26:彼らは天に上り、深淵に下り/苦難に魂は溶け
27:酔った人のようによろめき、揺らぎ/どのような知恵も呑み込まれてしまった。
28:苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと/主は彼らを苦しみから導き出された。
29:主は嵐に働きかけて沈黙させられたので/波はおさまった。
30:彼らは波が静まったので喜び祝い/望みの港に導かれて行った。
31:主に感謝せよ。主は慈しみ深く/人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。
32:民の集会で主をあがめよ。長老の集いで主を賛美せよ。
気になる言葉としては、私にとっては25節の「主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされた」という箇所。 読む人によっては、「神様のいじわる」と言いたくなってしまうかもしれない。 しかし、聖書全体から教えられるメッセージは、決して、神様がいじわるな方だというわけではない。
さて詩編作者の気持ちになって、この詩編箇所を今一度味わいたい。 「恵み深い主の感謝しよう、慈しみは永遠にあるのだから」という言葉をもって、主に感謝しよう。主が贖ってくださった人々は唱えよう、主は人々を苦しめる者から贖って、東西南北、あらゆる方角の国々から、集めてくださった(1-3節)。
人々は、海に船を出し、大海を渡って商売人となり(多少高慢な人間になったような面もあったのだろう)彼らは深い淵で主の御業・驚くべき御業を見ることになる(23- 24節)。 主は言葉を発することで、嵐を起こし、波を高くした(25節)。 よって、人々は天に昇ったり深淵に落ちるような気分になってしまい、苦難の魂が溶けてしまうかのよう(26節)。 また酔ってしまった人のようによろめいてしまい、知恵も働かず、なにもできなくなってしまう(27節)。 なにもできずにいる彼らは、大声で主に助けを求めてみる、すると、主は彼らを導きだした(28節)。主は嵐を静められ、波はおさまった(29節)。彼らは波が静まったのを喜び、目的地の港に導かれていった(30節)。だから主に感謝せよ、主の慈しみは深く、人々に驚くべきみ業を成し遂げる(31節)。民を集めて主を崇めよ、長老が集まった集いで主を賛美せよ(32節)。
21世紀の現代に生かされている私たちに、主なる神はこの詩編をもって何を語っておられるのか考えたい。紀元前に地中海を我が物顔に航海していた商人に突然、悪天候がおとずれたように、現代においても、順調にものごとが運んでいても、突然の逆風に遭遇し、なにもできなくなってしまうようなことがある。もう少し言うなら、「私の人生、とくに困っておらず、宗教にお世話になるつもりはありません。」と言う方とか「もうちょっと年を経て、キリスト教が必要になったら教会の門をたたきます。」といってくださる方もいたりする。 しかし、人生はいつ暗雲がたちこめ、真っ暗闇になってしまうか、何事もうまく行かずに意気消沈してしまうことにもなりかねない。 しかし、紀元後になって、主イエスが顕われてくださってから明確になったことだが、主イエスの信仰によってどんなことがおころうが人生は終わらない。 たとえこの世の命が終わったあとでも、主の慈しみは永久に続き、主が共に歩んでくださる。 どのようなことがおころうが、主が共にいてくださって、導いてくださっていることを覚えよう。 今週与えられた詩編箇所を読む中で、人生、順風の中にいる時から、主を畏れる信仰をもって生きるように導かれているように思う。
安達均