2015年5月31日LCR日本語部週報通算第1354号
May 31, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
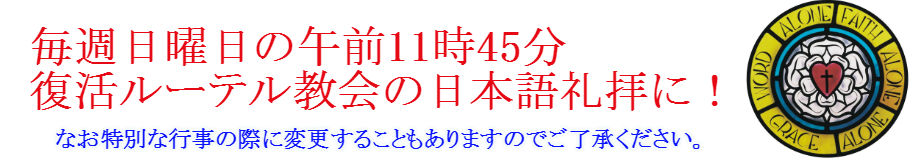
2015年5月31日LCR日本語部週報通算第1354号
May 31, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週は、三位一体主日の翌日6月1日から3日の聖書日課に与えられている詩編20編を読もう。いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの詩編20編を通して現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編20編
1:【指揮者によって。賛歌。ダビデの詩。】
2:苦難の日に主があなたに答え/ヤコブの神の御名があなたを高く上げ
3:聖所から助けを遣わし/シオンからあなたを支えてくださるように。
4:あなたの供え物をことごとく心に留め/あなたのいけにえを快く受け入れ〔セラ
5:あなたの心の願いをかなえ/あなたの計らいを実現させてくださるように。
6:我らがあなたの勝利に喜びの声をあげ/我らの神の御名によって/旗を掲げることができるように。主が、あなたの求めるところを/すべて実現させてくださるように。
7:今、わたしは知った/主は油注がれた方に勝利を授け/聖なる天から彼に答えて/右の御手による救いの力を示されることを。
8:戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが/我らは、我らの神、主の御名を唱える。
9:彼らは力を失って倒れるが/我らは力に満ちて立ち上がる。
10:主よ、王に勝利を与え/呼び求める我らに答えてください。
インパクトのある言葉として、7節の「今、わたしは知った。」
詩編作者の気持ちになって、与えられた詩編を振り返ろう。1節にはダビデの詩となっているが、おそらくダビデ王にしたがっていたイスラエルの民のための礼拝で詠う賛歌なのだと思う。2節以降で「あなた」となっているところは「ダビデ」におきかえても良いのだろう。2-4節では、苦難を経験しているダビデとその民だが、ダビデが支えられ、ダビデの神への供え物が受け入れられますようにと祈る。セラとなっているので、休止符か間奏が入る。そして5節にはいっても、祈りは6節まで続く。ダビデの願い、計画が実現するように。ダビデの勝利によって私たちは喜びの声をあげ、神の御名によって、勝利の旗を掲げることができるように。主がダビデの求めることをすべて実現してください。7節で「今、私は知った」と詠いはじめ、曲想はガラッと変わるようだ。主は油注がれたダビデに勝利を与え、救いの力を示される。戦力を誇るものがあるが、ダビデの民である我らは、主の御名を誇りたたえる。戦力を誇るものは倒れ、我らは主の力に満ちて、立ち上がることができる。10節では、再び、祈りの詩に戻り、ダビデに勝利を与え、呼び求めている我らに答えてください。
21世紀の現代にある私たちが、この詩編20編を読むとき、「あなた」はイエスに置き換えて、イエスに従うキリスト者たちの賛歌にもなるのだと思う。紀元前の世界と紀元後の世界で、人類が体験する苦難は同じように訪れる。しかし、「あなたの供え物・いけにえ」である十字架に供えられたイエス自身により、神が救いの力をさずけてくださっている救い主イエスが、イスラエルの民ばかりでなく、全世界の民に与えられている。イスラエルからしてみれば異邦人である私たちにも、勝利・救いがある。たとえ、イスラエルから東方の地の果てのような日本の民にも、また西方の地の果てのようなカリフォルニアにおいても、同じ救いがある。神とイエスが一体でさらに、神とイエスと一体である聖霊が、神の息が、世界中に吹き込まれている。私たちは、どんな苦難や困難や失敗を体験することがあっても、イエスの信仰を通して与えられる聖霊の力によって立ち上がる。
アーメン
安達均
ヨハネ 15:26-27, 16:4-15
主の慈しみ深い愛が、集まった会衆の上に豊かに注がれますように!
復活節をどのように過ごされただろうか? 4月5日がイースターだった。 多くの方々がこの礼拝堂に集まり、またイースターの祝会をしたのを覚えているだろうか?
それからまるまる7週間が過ぎ、今日で復活節は終わり、今、聖霊降臨を祝う時。 それぞれ、どんな気持ちでこの礼拝の時を迎えられただろうか?
いろいろな方々がいると思う。 家族も自分も健康良好、経済的にも今は安定している、良いイースターを経験したと振り返る方もいると思う。あるいは、自分は病気になる、あるいは事故にあった、怪我をした、あるいは家族がピンチに追い込まれている等々の状況にある方もおられると思う。
は「神も仏も無い。」という本が結構、日本で売れているようだ。 自分の人生まっさかさま、「神も仏も無い」といいたくなってしまう感覚はわからないでもないが、本当に「神はいないのだろうか。」
聖霊降臨日にあたって、さきほど使徒言行録2章を読んだ。 聖霊降臨の場面だ。 聖霊降臨というできごとが起きる前、弟子たちはどんな気持ちだったのだろうか。 それこそ、イエスの十字架の死は大ショックだった。
しかし、イエスは復活して、40日間、弟子たちに顕われてくださって、弟子たちを赦しかろうじて弟子たちの気持ちはつながっていた。 復活後40日目には、天に上っていってしまって、またリーダーがいなくなってしまうわけで、途方にくれるような状況になりかねなかった。
ただ、イエスは昇天前には「あなたがたの上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、地の果てに到るまで、わたしの証人となる。」 証人とは、イエスが神であるという証人になるという意味でとらえてよいと思う。
そして、今日使徒言行録2章で読んだように、聖霊降臨が起こり、信じられないようなことが起こる。異なる言語を話せるようになって、違う地域から集まってきた人々が通じ合えるようなことがおこる。 しかし、この聖霊が降りてきた事で、弟子たちはさらにどういう働きをするようになるのだろか?実際問題、彼らも迫害にあってたいへんなことになってしまう。 しかし 神の言葉に頼って、教会ができて、喜びををもって主イエスの福音を伝えることができた。そもそも聖霊って何者なのだろうか?
この聖霊が弟子たちにどう働くかを、より深く考える上では、イエスが十字架に架かる前に、語っていたことを振り返る必要があるのだと思う。 与えられたヨハネ福音書。 聖木曜日の晩にイエスは長い説教と祈りの言葉を述べる中で、弟子たちに聖霊が送られる約束をのべている。
さきほど読んだが、その中で、イエスは、「真理の霊が来ると、あなたがたを導いて真理をことごとく悟らせる。」 となっていたが、ギリシャ語から直訳するなら、「聖霊があなたがたを真理そのものに導く」と考えることができる。 ただ、イエスは聖霊という言葉は使わずに、「真理の霊」という言葉で聖霊のことを語っていたのは、とても重要。
真理の霊っていったいなんだろうか? 霊はよくいわれることだが、ヘブライ語やギリシャ語では、空気の流れ、風、息。 ただ、日本語で「真理」という言葉、英語だったら、”Truth”だが、イエスが伝えたかった言葉と同じ意味でわたしたちが理解できるか、ちょっと難しいものがあるのだと思う。
ヘブライ語では、「エメト」という言葉が使われていて、私たちは「アーメン」という言葉をよく使っているが、その意味は「その通り確かなことです。」という意味。 エメトとアーメンはもともと同じ言葉だそうで、エメトは確かに頼ることができるという意味。このような語源から考えてきて、真理の霊とは、本当に確かで本質なる神の息吹という意味。
お葬式などで読まれる有名な聖書箇所、ヨハネ14章6節には、イエス自身が、「私は道であり真理であり、命である。」といわれている。 真理とはイエスであるといえる。 イエスの語られていた、真理の霊があなたがたを真理を悟らせる、真理に導くというのは、聖霊によって、イエスの弟子たちが、イエスご自身に近づけるということ。
この地球にいるイエスの弟子たち、クリスチャンに、今も主なる神は、本当に頼ることのできる確かな神の息吹を送ってくださっている。 そして、その息吹は、イエスの弟子たちを、今日も真理なるイエスに近づけてくださっている。
イエスは徹底的に自分を低くし、自分を空にして、すべてを父なる神に捧げられた。そのようなイエスに、好むと好まざるに関係なく、近づいている。
復活節の過去、7週間、どんなだったかということを振り返る時、この世的には、いろいろたいへんなことがおこったということがあるかもしれない。 しかし、そのような中で、聖霊は確かに、一人一人に働いており、私たちを真理なるお方へと近づけている。 そこには、どんな苦しいことがあっても、真理なるたしかに頼ることができるものがそこにあり、喜び、希望を抱ける。 決してその苦しみが無駄になるわけではなく、すべてが良きにされる時がくる。
今日からは聖霊降臨後の季節が続く。11月の終わりまで、約6ヶ月もの間。 さらに次の6ヶ月を思うと、いろいろ不安を抱く方も多いと思う。 しかし、どんなことがあろうが、聖霊の力を信じているだけで、それで十分なのである。 主イエスの愛をいっぱいに受けて、聖霊の力により、主を愛し、隣人を愛する人に創られて、本当の喜びあふれる人生を歩んでいこう。 聖霊の働きにより、イエスの喜びと愛が集まった会衆の心の中にゆたかに注がれますように!アーメン
安達均
What is the Spirit of Truth?
John 15:26-27, 16:4-15
May the Gracious Love of our Lord be poured into the people in this sanctuary!
How was your Easter season? Do many of you, that attended Easter Sunday worship and luncheon, still remember what the sanctuary looked like? And how have you been since then?
7 weeks have passed since Easter and today we are celebrating Pentecost. How do you feel today, when reflecting upon the last 7 weeks?
Each situation is different. Some might be very thankful for their good health and financial stability, and feel that it was a good Easter season. But I am sure there are people who became sick, had accidents, were injured, or are facing financial difficulties. If you’re included in the later group, your Easter didn’t go as well as hoped.
In Japan, there is a book called “Kami mo Hotoke mo Nai” which means there is no God and no Buddha. Even though I am a pastor, I understand that we, as human beings, sometimes want to say these words.
On this Pentecost Sunday, we read Acts Chapter 2. The scene in which the Holy Spirit came down like doves came down as tongues of fire, and came down as strong wind. However, let’s reflect upon how the disciples were feeling before Pentecost. Right before Easter, they could not prevent Jesus’ crucifixion and they were in tremendous shock due to Jesus Christ’s death.
Then Jesus appeared among his disciples, forgave them, and breathed the Holy Spirit upon them on the first day of Easter saying “Peace be with you.” Jesus appeared to his disciples for 40 days, but in the end, he ascended into heaven.
I believe the disciples again wondered about their lives, even though Jesus said “You will have power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses of Jesus who is God, the savior, to the ends of the earth.”
10 days later, his disciples received the power and began miraculously communicating with people from different countries. The Holy Spirit enabled the disciples to speak different languages and spread the Word. However, looking back on the lives of first generation disciples, their lives were not easy and many of them were persecuted. Even though they would be persecuted like Jesus was, they joyfully conveyed the word of Jesus Christ and testified that Jesus of Nazareth was our Savior and Lord. What is the Holy Spirit? Why does the Holy Spirit work the way that it does?
In order to think about how deeply the Holy Spirit works for the disciples and us, we need to remember about what Jesus told his disciples even before the night he was betrayed and his crucifixion. On Maundy Thursday, Jesus promised that the Holy Spirit would be sent to his disciples.
A short time ago, I read the Gospel of John, Jesus clearly mentioned his promise that the Holy Spirit would be sent to his disciples. Jesus said, “When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth.” It is important to notice that in this instance Jesus uses the phrase “the Spirit of truth.”
What is “the Spirit of truth”? The Spirit is movement of air, wind, and the breath of God. How about “truth”?
In Hebrew, this word is expressed as “emt.” The root word of this word is the same as “amen,” which means “surely it is right and trusted.” Therefore, we can interpret that the Spirit of truth is God’s breath that we can truly trust.
Also, I just would like to mention that Jesus was saying “I am the way, the truth, and the life” which is often read during memorial services, but the point is Jesus himself is truth. So when Jesus said in today’s text, “When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth,” The disciples weret old to truly trust the words of the Father, God, and that they would guide them to Jesus, the truth.
Even today, the Father God is sending the His breath/word that we can truly trust, that is the Spirit of truth. That Spirit is guiding us to be true Christians, like Jesus, who humbled himself, emptied himself, and offered himself completely to the Father, God.
When you reflect upon the last 7 weeks, some of you had very challenging experiences, like Ryoko Higuchi and her family. Even through these situations, the Holy Spirit works beside us and guides us to the one, the truth. Whatever our situations are, the Spirit, God’s breath that we can truly trust is with us. The Spirit fills us with Joy and Hope.
From today, almost 25 weeks, almost half of the year, will be post-Pentecost season. Although you might fear or wonder what your life will be like for the next 6 months, believing in the Holy Spirit is enough to give a sense of calm. I pray that the Spirit of truth guides us according to God’s will. The Spirit of truth speaks Jesus’ words, so we have no reason to doubt what God wants for us. Amen.
Pr. H. Adachi
本日は礼拝後に5月の誕生祝いがありました。来週の礼拝は、礼拝後の軽食と交わりの時がありません。ご了承ください。
2015年5月24日LCR日本語部週報通算第1353号
May 24, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今年は5月24日が聖霊降臨祭。ペンテコステとも言われる。クリスマスやイースターのように、非宗教的な世界でもお祝いするような面があるお祭りと異なり、聖霊降臨祭はキリスト教会独自のお祝いなのかと思う。といっても、ペンテコステという言葉自体は、50日目という意味で、ユダヤ教ではイスラエルの民が奴隷としてエジプトで仕えてきた時代が終わるきっかけとなる過越祭から数えて50日目にエジプトからイスラエルに旅をするリーダだったモーセにシナイ山で律法が与えられるという記念の日でもある。さてそのようなことも覚えながら、与えられた詩編104編後半を読んでいきたい。 いつものように気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの復活節にあって現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編104編
24:主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお造りになったものに満ちている。
25:同じように、海も大きく豊かで/その中を動きまわる大小の生き物は数知れない。
26:舟がそこを行き交い/お造りになったレビヤタンもそこに戯れる。
27:彼らはすべて、あなたに望みをおき/ときに応じて食べ物をくださるのを待っている。
28:あなたがお与えになるものを彼らは集め/御手を開かれれば彼らは良い物に満ち足りる。
29:御顔を隠されれば彼らは恐れ/息吹を取り上げられれば彼らは息絶え/元の塵に返る。
30:あなたは御自分の息を送って彼らを創造し/地の面を新たにされる。
31:どうか、主の栄光がとこしえに続くように。主が御自分の業を喜び祝われるように。
32:主が地を見渡されれば地は震え/山に触れられれば山は煙を上げる。
33:命ある限り、わたしは主に向かって歌い/長らえる限り、わたしの神にほめ歌をうたおう。
34:どうか、わたしの歌が御心にかなうように。わたしは主によって喜び祝う。
35b:わたしの魂よ、主をたたえよ。ハレルヤ。
気になる言葉としては、24節にすべての創造が「知恵によって成し遂げられた。」と書いてある。神のお考えの中で、すべての創造が続いていることを覚える。
詩編作者の気持ちになって、与えられた詩編箇所を振り返りたい。 24節から26節では、いかに主の御業がすばらしいことか、地も海も、地上に住むものも、海の中に住むものも、すべて主の知恵、つまり神の考えによって創造された。27節から30節では、すべての生物の創造は今も続いており、創造されたものは主に望みを置き、主から与えられるもので満たされる。主が見渡してくださらなかったら恐れが生じ、生物の存続は、主なる神の息を注いでくださるかどうか次第である。 30節から最後までは、その息によって、地は新たにされる。主が見渡せば、地は震え、主が地を触れると噴煙もあがる。主の栄光が続くように、主のお考えが喜び祝われるように。だから私も生きる限り、主を賛美しよう。 以上振り返る中で、与えられた詩編箇所での詩編作者の大きなポイントは、神の知恵があって、地も海もそこに住むものも創造された。その知恵は現代の言葉でいえば、エコシステムとも言うべきものなのかもしれない。またユダヤ教のペンテコステを思う時、そのエコシステムには、イスラエルの民に与えられた戒め(律法)も含まれているように思う。
さらに、与えられた詩編箇所が21世紀に生きるわたしたちに何を語っているのか思いをめぐらせたい。 現代の言葉でいうエコシステムが神の知恵であることを書いた。そして来る日曜日には、キリスト教会では聖霊降臨日を控えている時に、そのエコシステムの中に、絶対に欠かすことができない、神の息、聖霊の存在を覚える。この詩編は紀元前数百年前に詠われはじめたものだが、ユダヤ教の伝統、そしてそれを引き継ぎキリスト教の伝統の中で、現代の21世紀にも詠われる。主なる神の息の大切さを思い出させてくれる。 私たちの目にははっきりとは見えるものではないが、主なる神の知恵、考えが秘められている、聖霊の働きについて、聖霊降臨日に向けてさらに思いを巡らせていきたい。
この時期、復活ルーテル教会の信仰者たち、またその家族や友人でも、病の中にある者が多い。ICUに入っている者も私の知るだけで二人いる。 聖霊の働き、癒し、励ましが注がれるように祈りつつ。
アーメン
安達均
ヨハネ17:6-19
聖霊の働きにより、イエスの喜びと愛が集まった会衆の心の中にゆたかに注がれますように!
洗礼を受けて、クリスチャンになるということは、天国に行く列車の切符を手にすることなんです。 という方がいる。そのような比喩は、たしかにそういう面はあると思う。しかし、二点ほど付け加えないと思うことがある。 第一点は、洗濯してなくなったりしないように、切符は紙ではできていないこと。洗礼をうけ、聖なるものとされ、キリストの十字架のしるしを受けることそのものが、切符である。
第二点目は、これから説教でお話することすべてが第二点目ということになってくる。 洗礼を受けた者は、ただ列車に乗って何もせずに天国に行くわけではない。じゃ、どんな列車なのだろうか?
1970年代、私はまだ日本で中学生だったが、日本でも大ヒットしたディスコでよくかかった The O’ Jaysというソウル3人組が歌ったLove Train という曲があるが、最初の1分程度だけでもそれをちょっと見ていただけたらと思う。 踊りたくなってしまうかもしらないが、どうぞおけがのないように。
今ご覧いただいたビデオに出ていた、列車が走っているイメージと子供たちのイメージがオーバーラップしていたのが、とても面白いと思った。 そして、この説教がどういう方向に話が展開するのか、もうわかってしまった方もいるかもしれないが、この列車のことはまた説教の後半で話したい。そして、与えられた福音書の内容に入っていきたい。ヨハネ17章はイエスの長い祈りで、苦しみを受ける前日の晩、弟子の一人に裏切られ、他の弟子たちからも見放される前に、弟子たちのために祈った祈り。その祈りは確実に聞かれ、当時の弟子たちにとっては現実のものとなり、現在の弟子たちにも現実になりつづけている。
イエスの17章の祈りには、6点もしくはそれ以上の要点があると思う。 しかし、私は、11節から16節の中のポイント、3点だけにしぼって、お話ししたい。 その第一番目のポイントは、イエスが十字架刑に架かる前に、弟子たちが、守られるようにとにかく祈ったところ。そしてすべての弟子たちが神とともにひとつになるようにと祈られたこと。
ヨハネ福音書は90年代に記載されたというのが世界中の一般的な見方だが、当時すでにキリスト教徒たちはたいへんな迫害にあっていた。そのような時代背景の中で、福音書記者ヨハネは、イエスが激しく祈られたことを強調しているようにも見える。イエスの祈りはすさまじい。たとえ、弟子たちが迫害され殺されてしまうようなことがあったとしても、イエス自身が父なる神によって守られ父なる神と一体で、永遠の命を得ていたように、弟子たちも一体となり、神から守られ永遠の命にあることを祈られたのだと思う。
第二番目のポイントは、弟子たちがイエスの喜びで満たされるようにと祈っている。その喜びとは、たとえ翌日十字架刑にかかろうが、イエスに喜びが満ちていること。それは、新幹線でグリーン車の切符を手にするような喜びとは全く種類の異なる喜び。
イエスが父なる神と一体で、父から喜びを与えられているように、弟子たちも一体で同じ喜びで満たされるように祈っている。そして、弟子たちとは、当時イエスといっしょにいた弟子たちだけではなく、後の弟子たちをも含めて、つまり私たちも含めて、喜びで満たされるようイエスは祈ってくださった。
最後のポイントは、世に遣わされる弟子たちを聖なるものとしてくださいと祈られたこと。イエスは翌日には、十字架にかかる、そして3日後には、復活して40日間は弟子たちの間に姿を現されたが、復活後40日目、天に昇っていかれる。そのように、父なる神と一体なる聖なるイエスは、この世にいなくなる。しかし、その聖なるイエスが存在し続けるがごとくに、弟子たちも、聖なるものとしてくださるように、そして世に派遣されるように祈られた。派遣されるということは、隣人たちへ仕えるようにと祈られた。
さて、キリスト教徒、イエスの弟子になるとはどういう意味か今一度振り返りたい。洗礼を受けて、聖なるものとなり、国籍は天にあるものとされる。それは、天国行きの切符が保証されるともいえる。かといって、なにもせずに天国に行けるということではない。 イエスが当時の弟子たちにまた将来の弟子たちに祈られたように、私たちは皆、世に遣わされ、人々に仕える僕とされていく。
この列車の比喩は、受動的な列車ではなく、むしろ積極的な列車である。 キリスト教徒たちは、列車に乗っているというより、むしろ列車そのものがキリスト教徒たちというべきなのだと思う。
この列車の比喩は、マルティンルターの馬車の比喩を思い出される。ルターいわく、あなたがたは、キリスト者の生活は馬に引かれたワゴンにのって、その馬を操るようなものだと思っているかもしれない。 しかし、実際は、キリストが馬を操り、私たちは馬だと。神が方向性を定め、私たちが、愛をもって、自分を捨てて人に尽くすように仕向けている。
私はCCN、カウンセルのミーティングに出たり、また、最近ではストラテジックプランにMeaningful Program and Ministry の会議にも出たりしているが、教会のため、世のため人のために尽くしている方々を見るにつけ、どれほど私も喜びで満たされるか。また今、この毎週の礼拝そのものが、神の喜びと愛で満たされイエスが私たち一人一人に仕えてくださっているように、私たちが礼拝に出ていること事態が、人々に仕えあっていることを示している。
これはイスラエルからしてみれば、地の果てとも思えるようなハンティントンビーチで、また世界中の各地で、おこっている。それはもともと2000年前に、弟子たちが守られ、喜びで満たされ、聖なるものとされ、人々に仕える者となって世に派遣されるようにと、イエスが祈られたことが、現実のものとなっている。このように聖霊が、私たちを世の人々のために仕える者となるようにしてくださっている。
May We Live for Others
John 17: 11-19
May the Holy Spirit, Joy, and Love come to the hearts of the people gathered in this sanctuary!
There are people who say, “To be a Christian is something like getting a train ticket to heaven.” It might be true, but I would like to add two more things to that metaphor.
Number 1: That ticket isn’t made of paper so you cannot lose it by putting it in the washing machine. The ticket is like an e-ticket, being baptized, sanctified, and marked with the cross of Jesus Christ is the ticket, so you do not need to show your driver’s license or passport to claim it.
The second point I would like to talk about is actually the content of the rest of my sermon. These people, baptized people marked with the cross of Jesus Christ, are not just boarding a train that goes to heaven. So what kind of train are we talking about?
In the early 1970s, during my middle school years, there was a great hit song called “Love Train,” sung by R&B group The O’ Jays. I would like to show a little bit of a YouTube video for that song. Some people might want to dance, please feel free to do so in your seat.
HERE: SHOW THE YOUTUBE VIDEO
I think the images we saw are very interesting and some people may have noticed where I am going with my message. But, I will come back to the image about the train at the end of my sermon. Here, I would like to dive into the Gospel text. John Ch. 17 is a long prayer that Jesus prayed at Gethsemane in the night right before he was betrayed. That prayer was surely heard by the Father, God, and everything was realized as he prayed and his prayer continues to be realized to this day.
There were several points, I think more than five, in that prayer, but I would like to focus on only three points from Scripture. The first point was that before he was crucified Jesus prayed that his disciples would be protected and continue to have eternal life. Like he and the Father were one, he prayed that all of his disciples would become one.
The Gospel of John was probably written at the end the first century, ca. 90s. At that time, Christians were already suffering severe persecutions and John may have been the only disciple still living. Therefore, John wanted to make sure that Jesus prayed very hard that, even though his disciples were persecuted and killed, they had eternal life in oneness with God and that they were protected by the Father like Jesus was protected by the Father.
The second point of the prayers was that Jesus prayed that the disciples would be filled with His Joy. This kind of Joy would endure even when he knew that he would be crucified the next day. That Joy is very different from having a first class ticket to board a special bullet train.
Jesus himself is together with the Father and he is filled with Joy from the Father. Likewise, he prayed that his disciples would be filled with the same Joy Jesus was experiencing. And Jesus was not only praying for his current disciples, he was praying for all disciples in later ages, as well, including ourselves who share the same faith in Christ.
The last point of the prayer is: Jesus prayed for the disciples to be sanctified. As a matter of fact, the sanctified Jesus Christ who was together with the Father, God, would be killed on Friday, and on Sunday, he was risen and present among the disciples but then 40 days later, he ascended to heaven. The sanctified Jesus physically disappeared from the disciples after his ascension.
Even though he would ascend to heaven, he prayed to God that the disciples, His friends, would be sanctified and sent to the world to serve their neighbors and the Lord.
Let’s reflect on the meaning of being Christian. Being a baptized Christian , at that moment, our nationality surely changes to “heavenly.” In other words, you could say that our ticket to heaven is secured.
However, that does not mean that we just get to go to heaven without doing anything. As Jesus prayed for his current disciples and for future generations of Christians, we are all always sanctified and sent out into the world to selflessly serve our neighbors and communities.
This metaphor speaks to rather than just passively boarding a train, Christians are expected to be active in the world. Christians should live for others. They are filled with the Love and Joy of Jesus Christ and they become the train itself so that they may carry God’s enduring message to the world.
This metaphor reminded me about what Martin Luther said, “We might think being a Christian and living our lives is like driving a wagon, but no, we are the horses pulling the wagon, and the driver is Jesus.” God gives our lives direction. Christians should lovingly and selflessly serve the Lord and our neighbors.
There are examples of selfless service at Resurrection Lutheran Church. I have been attending LCR Council as one of the pastors and I have also been attending CCN board meetings. I have been attending Meaningful Program and Ministry meetings, for the last several weeks, as well. Every time I attend these meetings, I witness people gathered together filled with the Joy and Love of Christ and sent by the Holy Spirit to serve the Lord and to selflessly serve others.
Not only in those meetings but also here in this sanctuary; those who worship every Sunday are filled with God’s Joy and Love.
Our presence in this sanctuary signifies our willingness to serve the Lord and to serve one another as Jesus is serving each one of us.
This happens even in Huntington Beach, or half way around the world in Israel, and in other parts of the world too, because 2000 years ago at Gethsemane, in Jerusalem, Jesus prayed that all disciples be protected, filled with Joy and Love, be sanctified by the Father, and be sent out into the world to selflessly serve others in his Name. As such, the Holy Spirit enables us to live for others, and not just for ourselves. Amen.
Pr. H. Adachi
2015年5月17日LCR日本語部週報通算第1352号
May 17, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
アメリカ福音ルーテル教会のパシフィカ教区内では10以上の原語で伝道が行なわれている。アメリカ合衆国には、いわゆる出稼ぎに来た、そしてそのままいることになった方々、普段の経済的生活は苦しいという方々にとって、英語ではない自国の原語で伝道が行なわれていることは、ニーズも高く人々が集まる。しかし、何世代か前からアメリカ合衆国に移民してきた家系あるいは移民一世でも、経済的には困ることはないと思われている方々には、はっきりいってキリスト教は必要ではないと思う方々が多くなってくる。そんなことを思いつつ、今日読む詩編は115編。詩編を読もうでは初めてとりあげる。気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神はこの復活節にあって現代のわたしたちに何を語りかけているか思いを巡らせよう。
詩編115編
1:わたしたちではなく、主よ/わたしたちではなく/あなたの御名こそ、栄え輝きますように/あなたの慈しみとまことによって。
2:なぜ国々は言うのか/「彼らの神はどこにいる」と。
3:わたしたちの神は天にいまし/御旨のままにすべてを行われる。
4:国々の偶像は金銀にすぎず/人間の手が造ったもの。
5:口があっても話せず/目があっても見えない。
6:耳があっても聞こえず/鼻があってもかぐことができない。
7:手があってもつかめず/足があっても歩けず/喉があっても声を出せない。
8:偶像を造り、それに依り頼む者は/皆、偶像と同じようになる。
9:イスラエルよ、主に依り頼め。主は助け、主は盾。
10:アロンの家よ、主に依り頼め。主は助け、主は盾。
11:主を畏れる人よ、主に依り頼め。主は助け、主は盾。
12:主よ、わたしたちを御心に留め/祝福してください。イスラエルの家を祝福し/アロンの家を祝福してください。
13:主を畏れる人を祝福し/大きな人も小さな人も祝福してください。
14:主があなたたちの数を増してくださるように/あなたたちの数を、そして子らの数を。
15:天地の造り主、主が/あなたたちを祝福してくださるように。
16:天は主のもの、地は人への賜物。
17:主を賛美するのは死者ではない/沈黙の国へ去った人々ではない。
18:わたしたちこそ、主をたたえよう/今も、そしてとこしえに。ハレルヤ。
気になる言葉、2節にある「彼らの神はどこにいる。」という人々の言葉。
詩編作者の立場を想像しながら、115編を振り返りたい。全部で18節と長いので、4つの部分に分けてまとめてみる。1-2節は、わたしたちの栄光ではなく天にいる主の栄えが輝くようにという祈りではじまり、諸国の民はわたしたちの主の存在が見えないから「彼らの神はどこにいるのか」と非難する。3—8節では、わたしたちの神は天におられ、主の思いのまま、すべてが行なわれている。諸国の民が崇拝している偶像は、なにもすることができない。 9-16節では、ユダヤの民の中でも、偶像に頼ってしまったもの、主に頼ることができない者もいたが、助け、岩となってくださる主を皆が頼るように。頼れずにいるユダヤの民を祝福してください。天地の創り主で、天におられる主によって、地上にいるすべての民を増やし、祝福してください。天は主の領域で地は民に与えられた賜物。17-18節で、主を賛美することは決して虚しいものではない。わたしたちこそ主を永遠に賛美しよう。18節の「わたしたちこそ」と書いた「わたしたち」には、ユダヤの中で主を崇拝してきた者だけではなく、ユダヤの中で偶像礼拝をしてしまっている者、あるいは諸国の民で偶像礼拝している者にも、主の御心により、皆が心をあわせて主を賛美するようにという思いがあるようだ。
主なる神が、詩編115編を通して21世紀に生きるわたしたちに語りかけてくることは何なのか、思いを巡らせたい。 現代、発展途上国においてキリスト教もたいへんな勢いで伸びているし、また、イスラム教はもっとその勢いは強いのかもしれない。経済的な困窮におかれている者の方が絶対なる神、宗教へのニーズが高まってしまうという現象はおこるのだろう。しかし、その逆は、経済的に豊かな状態になると、概ね、宗教へのニーズは下がってくるというのが社会現象なのかと思う。 この詩編115編の、偶像に頼る諸国の民、あるいはユダヤの民の中でも主に頼れなかった者も含め、彼等は、現代でいう裕福な人々でその中でも「わたしには宗教はいりません。」あるいは「これまでとくに困ったことはないので、救い主は必要としていません。」といっておられる方々に思えてくる。 実は、主なる神は、そのような方々に語りかけているような気がしてならない。偶像というのは、現代でいえば、お金やその数字が示している大きさに頼ってしまっていることではないだろうか。いくら順調な生活を送っていても、実は主なるお方がいなければ、その主なるお方が私たちの自分勝手な思いを赦してくださっていなければ、私たち(信仰者もそうでない方々も)の命はありえない。
アーメン
安達均
ヨハネ 15:9-17
主の恵みと平安が豊かに注がれますように!
2011年に日本で大人気番組となった「まるものおきて」というドラマがある。アメリカでもここ数ヶ月にわたって放送されていた。
若い夫婦に、男女の双子が生まれるが、あまりの育児のたいへんさに、母親は精神が病み、育児ができなくなってしまう。父親はシングルファーザーとして、双子を育て始めるが、がんになり、急逝してしまう。
父親の学生野球部時代の親友、護がシングルファーザーとなることを決意し、双子を引き取る。もちろん、たいへんなことだった。護は、血のつながっていない子供たちに、俺たちは家族だと説き、子供たちは、なぜか護を「まるも」と呼ぶようになる。
毎回のドラマでは、護が二人の子供との間で「まるもの掟ノート」を作り、多難な中にも、喜びあふれる家族生活が描かれる。毎週のドラマの中で、掟が一つづつ、綴られる。ある回では護と娘の関係が悪くなり、話もしなくなってしまうようなことが起こる。しかし、護は、「好きでも嫌いでも家族」という掟を作る。
さて、まるもの掟の話は、今日の説教の最後にまた話すとして、与えられた福音書、イエスの掟の話に入る。イエスは、「互いに愛し合いなさい。これは私の掟」と今日の福音書箇所の中盤で述べ、最後は「互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。」と言う。
命令とまで言われてしまうと、「愛する」ということは、命令されて、「愛する」ことなのだろうか? と疑問を持つこともいるかもしれない。あるいは、「互いに愛するように」ということは、相手も自分を愛するし、自分も相手を愛すること。となると、相手が愛してくれているかどうかわからない、いやむしろ私のことを嫌っているのに、「互いに」と言われても、困りますという方もいるのではないだろうか?
このように考えると、イエスの言われた掟や命令は、すんなり受け取ることができずに、むしろ質問をしたくなるという方が居ると思う。これらの質問を考えるにあたって、与えられた福音書箇所の中では、イエスが「わたしがあなたがたを愛してきたように」という言葉を繰り返し述べた上で、この「互いに愛し合いなさい」という掟を述べられていることに注目したい。
イエスが弟子たちを愛する愛し方はすごいのだ。今日の福音書箇所は、明日十字架にかかるという前の晩、つまり聖木曜日に語った言葉。そして、その後には、一人の弟子たちからは裏切られ、ほかの弟子たちからも見放されて十字架にて死に葬られる。
しかし、父なる神は、徹底的に愛する子イエスを墓からよみがえらせ、子イエスは、そんなにひどいことがあったのに、友なる弟子たちの前に現われ、いっさい咎めることなく、「あなたがたに平和があるように」といって、弟子たちを赦される。
この十字架の死と復活を通して示されたイエスの弟子たちへの愛は、たとえ弟子たちが、人間としては欠けることの多い者たちであろうが、無条件に愛してくださる本当に慈しみ深い愛だ。その愛が示されたことは、互いに愛し合いなさいとは、命令というより、キリスト者同志がおのずと互いに愛さざるを得なくなるような、不思議な働きかけに思えてくる。
また、キリスト者同志が互いに愛し合うように導かれているのはもちろんだが、キリスト者を嫌う方、避ける方、無関心な方、あるいは極端な話、非難し攻撃する方もいるのが現実だ。イエスはヨハネ福音書の13章の中でも、「互いに愛し合いなさい。」ということを述べているが、その35節では、「互いに愛し合うならば、あなたがたがわたしの弟子であることを、皆が知るようになる。」という言葉があった。
そこには、互いに愛しあうキリスト者の存在が、最初は12人しかいなかった弟子たちが、全人類に対して、「互いに愛し合う」存在になっていく働きかけがあるように思う。 それは、わたしたちの力ではない、わたしたちの想像もつかないような、聖霊の働きかけが、ただよっているように思う。
今日のポイントは、まず、神が、そして子なるイエスが、弟子失格とも思われてもしかたがないような弟子たちをも、愛してくださっていることをわかること。 そして、その愛が、現代のキリスト者にも、脈々とつながっていることを感じることが大切なのだと思う。
そして、互いに愛し合うという行為は、キリスト者同志という枠を超えて、互いに欠けの多い家族の間でも、また、いがみ合ってしまうことの多い国々や人種や文化を超えて、互いに愛し合うということに導いているのではないだろうか。
「まもるの掟」に出てきた、護が書いた「好きでも嫌いでも家族」という掟、たしかにそうなのだと思う。 それは、まもると双子の子供たちの家族という単位で、その掟はかかれたが、実はもっともっと大きな、神が創造された地球という単位で、そこに存在する自然、資源、食料を共有する地球単位の家族の意味にもとらえることができる。
今日は母の日で、最初スーッと通りすぎてしまったが、まるもの掟のドラマでは、双子を生んだが子育てができなくなってしまった母親がドラマには登場していた。 私は、母の日を迎えるたびに、どうしても、このドラマにちょっとだけ登場するような子どもを生んだが、子育てができない。 あるいは、子供が欲しくても、さまざまな事情で生むことができていない女性のことも覚える。
どんな境遇にあろうが、そのまっただなかに、イエスがおられ、よりそってくださっている、そして、イエスが愛してくださっている。今日の母の日は、決して子供のいる母ばかりではなく、全女性に対する神からの愛・赦しがあり、また互いに愛するようにという励ましがある。
ちなみに教会で花を用意させていただいた。赤いチューリップの花言葉は、愛の告白であり真理の愛、またトルコキキョウは、優美、希望、感謝などがあるという。赤いチューリップと紫トルコキキョウを受け取っていただき、赤は、主イエスから私たち人間への熱烈な無条件の愛を覚え、紫のトルコキキョウからは、人々からの感謝・愛が注がれていることをしっかり覚えていただければ思う。
アーメン 安達均
“We Are Family Together Whether You Like It or Not”
John 15:9-17
May the Grace and Peace of Jesus Christ be poured into your hearts!
There is a Japanese TV drama called “Marumo No Okite” meaning “Marumo’s Law” which became very popular in 2011. Since this was broadcast in the US recently, you might have seen it.
Twin babies were born to a young couple. However, the mother became emotionally unstable and could not continue raising the babies and left the family. Her spouse became a single father and tried very hard to raise the children, but, he was diagnosed with terminal cancer and suddenly passed away.
Then his best friend and teammate from their college baseball team, “Mamoru” decided to be their adoptive father and gained custody of the twins. Of course this was not an easy thing to do. Mamoru taught them that they are family even though he was not their biological father. The children, Kaoru and Yuki, called Mamoru “Marumo” because they couldn’t pronounce his name. They started their sometimes rocky but ultimately loving, unique family life together.
The program was a weekly drama and every week, Mamoru wrote one law in his notebook named “Marumo No Okite.” One of the laws in an episode was “We Are Family Together Whether You Like It or Not.”
I will get back to Marumo’s Law at the end of this message; now let’s dive into today’s Gospel. Jesus said repeatedly, “Love one another. This is my law.” He even said “Love one another” is a commandment.
If people are told that to love one another is a commandment, there will be people who question “Can human beings love one another when we are ordered to do so?” Or some people may think that someone does not love them, and consequently “loving one another” may be very difficult for them to do…
When we think about usual human behavior, the commandment that Jesus gave might be difficult to accept right away. People will ask questions first. To search for answers to these questions, we look to John’s Gospel. In that Gospel, Jesus said twice “As I love you” before he gave this commandment.
The way Jesus loved his disciples was something unimaginable when the disciples were listening to Jesus’ discourse. The Gospel we are reading today was spoken during the night in which he was betrayed. In other words, this discourse was one day before he was crucified. On the Maundy Thursday, after he finished his speech, one disciple completely betrayed Jesus, and then the other disciples left Jesus, denied knowing him and ran away, realizing that he would be crucified. The disciples were fearful that they would be captured as well.
In reality, Jesus was crucified and died. However, the father, God who loves Jesus so earnestly resurrected Jesus. Not only was he resurrected, Jesus himself appeared in the midst of disciples and did not accuse them of betrayal but forgave them saying, “Peace be with you.”
The love shown to the disciples through the death and resurrection of Jesus Christ, the love expressed through the cross, was unconditionally given to the disciples. Even though the disciples were imperfect and they had many shortcomings, Jesus still loved them. The Love of Jesus is unconditional and filled with mercy. The fact that this unconditional love was revealed to his disciples caused them to love one another spontaneously and naturally. “Love one another” is not really an order, but a code of conduct.
This approach encourages Christians to love one another, but in this world there are people who avoid Christians, are disinterested in attending church or, in the extreme, hate Christians. I would like to quote John Chapter 13, Jesus said “everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another.”
That is the core code of conduct for his disciples, only 12 in the beginning, who love one another, are to approach all human beings in the world asking them to love one another. This is not really my approach but it’s a power that we cannot fully comprehend, i.e. the work of the Holy Spirit, and it encourages all human beings love one another whether people like it or not.
The law in the Marumo’s Law episode “We Are Family Together Whether You Like It or Not” is true. Family does not only refer to the family of Mamoru and the twins, but also includes God’s family who live together in this world. All people are sharing the same resources, natural sites, and food. For the good of the planet and future generations, people must learn to love one another, even though people might disagree on a personal level.
Today is called “Mother’s Day.” At the start of this message, I quickly mentioned the twins’ biological mother and her emotional difficulties. On this Mother’s Day, I would like to include all women who have experienced difficult situations and include them in our thoughts and prayers. There are women who bore children but could not raise them or those who wished to have children but could not conceive.
Whatever our situations are, in the midst of challenges and difficulties, Jesus Christ is here among us; Jesus loves us, forgives us, and encourages us to love one another. Despite our shortcomings Jesus still loves us. His love and mercy are enduring and, as such, we should try to live up to his code of conduct that asks us to love others, regardless of our personal feelings. Amen.
Pr. H. Adachi
礼拝後は安達牧師と男性軍が女性に感謝し、焼きそばの食事会がありました。
2015年5月10日(母の日)LCR日本語部週報通算第1351号
May 10, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin