2015年3月22日LCR日本語部週報通算第1345号
March 22, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
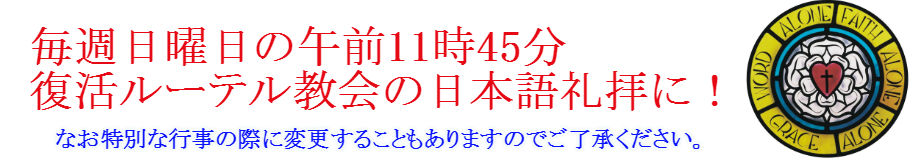
2015年3月22日LCR日本語部週報通算第1345号
March 22, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週は聖書日課では3月23-25日に与えられている詩編119編9-16節を読む。いつものように、主なる神に心を集中させて読んでいこう。そして、気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神は、現代の私たちに何を語っているのか、思いを巡らせよう。
詩編 119編
9: どのようにして、若者は/歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉どおりに道を保つことです。
10:心を尽くしてわたしはあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから/迷い出ることのないようにしてください。
11:わたしは仰せを心に納めています/あなたに対して過ちを犯すことのないように。
12:主よ、あなたをたたえます。あなたの掟を教えてください。
13:あなたの口から与えられた裁きを/わたしの唇がひとつひとつ物語りますように。
14:どのような財宝よりも/あなたの定めに従う道を喜びとしますように。
15:わたしはあなたの命令に心を砕き/あなたの道に目を注ぎます。
16:わたしはあなたの掟を楽しみとし/御言葉を決して忘れません。
気になった言葉は何だろうか。 私の場合は、15節の「あなたの命令に心を砕き」という言葉。「心を砕く」というと、「心配する」とか「配慮する」という感覚で使われていることが多いかと思う。しかし、原語のヘブライ語や英語に訳された言葉などを参考にして、つきつめて行くと「熟考する」という意味なのだと思う。
詩編作者の時代にさかのぼってみて、作者がこの詩編の言葉にこめた意味を想像していきたい。 詩編119編には22文字あるヘブライ語のアルファベットの各文字ではじまる22の詩が収められている。本日の箇所は、二文字目のBに相当する言葉ではじまる詩。 1-8節はAではじまる言葉で、基本中の基本ともいうべき教訓が書かれているともいえる。 そして二つ目の詩では、最初の節の言葉から若者への教訓にフォーカスしているようだ。 一節づつ考えていきたい。 いったい若者はどのように清き道を歩んでいけば良いのか、それは主の言われたとおりの道を歩み続けること(9節)。 心を尽くして主に尋ねもとめて、主の教えからはずれてしまうことがないように(10節)。主の言われたことを覚え、主に過ちを犯すことがないようにすること(11節)。主よ、賛美します、あなたの掟を教えてください(12節)。主が語られた裁きも自分で物語ることができるように(13節)。財宝などを喜ぶのではなく、主の定められた道を歩むことこそが宝であり喜びとなりますように(14節)。主の訓示をじっくり観想し、主の定められた道を敬って歩むように(15節)。主の掟こそ楽しみとし、主の言葉を覚えるように(16節)。
この詩編箇所を通じて、主なる神は現代のわたしたちに何を語りかけてくださっているか考えたい。 ユダヤ教信者の家族では、現代でも、親が子に、じっくりユダヤ教のトーラ(律法)を教えるという。日本語ではトーラを律法と訳してしまうが、どちらかというとさまざまな生活上の基本であり、旧約聖書のなかでも最初のモーセ五書に残された掟、「教訓」として捉えたらよいと思う。そして主イエスキリストは、最も重要な掟に関して次のように語られていたことを思い起こす。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』 律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」 現代の生活では、モーセ五書や詩編が著された時代とは大きく異なる環境の中に置かれており、モーセ五書では語られていない教訓や掟を自分たちで決めなければならないこともあるのかと思う。たとえば、夜中でも電気をつけて、本を読んだりすることもできる。あるいは夜中に映画を見に行ったり、あるいは友人と遊びにいったりもすることができてしまう。 しかし、いろいろな自由度があるなかで、行動規範は、常に「主なる神を愛する。隣人を愛する。」を年頭におき行動するかどうかになるのかと思う。四文字熟語で「敬天愛人」という表現もできるが、その意味は深く、熟考して行動する必要がある。 現代の親や教師たちは、こどもや生徒たちに、このようなことを教える大切さがあるのだと思う。 ルーテル教会が母体となって100年以上前に建立された九州学院を1月に訪問したが、学院の教訓が「敬天愛人」であることを思い出す。
安達均
John 3:14-21
救い主イエスの恵みと平安が私たちの心に注がれますように!
私は牧師になる前は医療電子機器の会社に勤めていた。アメリカの市場で何千台もの機器を病院に納めさせていただいた機械に脳波形があった。 脳波計とは患者の脳波を測定し、記憶装置に治め、脳の解析の手助けをする。使用目的の一つに睡眠の解析がある。
睡眠解析をする件数は、90年代に飛躍的に増大した。というのは、アメリカ人の10人に一人は睡眠障害があるといわれだしたから。学会などにも参加して、医師と対話する機会もあった多かった。 学んだことのひとつに、睡眠障害の7割方は、呼吸系の問題。睡眠時無呼吸になってしまったときに、呼吸を助けるマスクをして対処している方が家族にいたり親戚にいる方もいると思う。
残りの3割は呼吸系の要因ではなく、じつにさまざまな要因で、脳神経に関する原因であるが、その機序は複雑とのことだった。 ある医者は、残りの3割の不眠症は、本当に、それを病として治療することが良いのかどうか疑問であり、かなりの場合は、自分は治療をしないということを述べていた。 神経が高ぶってしまう要因を、それは千差万別なのだ
眠れなくなってしまった時に、神経を他のことに向けるというこがよく行なわれる。数を数えたり、ゲームをしたり、LCRのサイトにアクセスして私の説教の録音を聞いてもらうのも良いかもしれない。
いったいどうしたらよいのだろうか? 正統的な手段としては、私は神に祈ることかと思う。しかし、祈ることとは、意識して祈るわけで、眠らないこと。今年の聖句としてあげているコロサイ人への手紙には「目を覚まして、感謝を込め、ひたすら祈りなさい。」と書かれている。なぜ祈ることが私たちの睡眠の手助けをするのだろうか?
エピスコパル教会牧師、バーバラブラウンは眠れないという感情をそのまま信頼して、それから逃れようとするのではなく、さらにがけっぷちに近づくように、その眠れなくなっている要因をさらに深く考えようとしたらどうだろうかと書いている。心理学者のバイブルとまでいわれる診断と統計によれば、愛する人を亡くして悲嘆に暮れる日々は2ヶ月までとし、もしそれ以上に及ぶならうつ病と診断し処方薬を勧められてしまうそうだ。バーバラブラウンは、西洋の文化が暗い感情を恥として、ふたをしてしまう、拒絶してしまうようなところがあると指摘する。しかし、暗い感情をただおいやってしまってよいのだろうか?
心理療法士ミリアムグリーンスパン氏は暗い感情の治療なる本を書いている。彼女の母はホーローコーストから逃れた人で、彼女の母は戦後10年、率先して嘆き悲しんだという。あのような大量虐殺ということに対して、10年でも短いのかもしれない。グリーンスパン氏は、どうしようもない暗い感情なんというものは存在するのではなく、それはやりきれない感情にただ未熟な対応をしているだけに過ぎない。そもそも感情というものは、人間から何かをとりだす必要のある純粋なエネルギー、私たちを眠りから覚めさせて、私たちが何か知る必要があることを教え、私たちの心の周りに凝り固まってしまっているものを壊して、私たちが行動するように仕向けているものだと述べている。
暗い感情というものは、心の奥にある人々とは分ち合いたくない、あるいは、考えたくも無いことでも含まれているのだとおもう。それらは恐れや恥に起因している場合もある。これらの感情は人々を極端に内向的にさせ、人との対話が難しくなったり、自分に価値がないものだとしてしまったりする。また過去の失敗や事故などによって、とてつもない弱い立場においやってしまうことがある。 実にさまざまな問題から神経がやられてしまうことはある。不眠症になったから西洋医学によって治療しなければならないという気持ちになる人が多い。しかし、バーバラブラウンは、暗闇の感情に対して我慢ができていないのだと指摘する
脆弱、勇気、価値、恥といったような内容の研究をしているブルーネブラウン教授は傷つきやすい心とは、恥や畏れ、そして自分の価値について紋々とする時の核心的な問題だと指摘する。しかし、そのような時に、傷つきやすい心、社会への帰属意識や愛情を受け入れる心に生まれ変わる場合があるという。
今日一人の医師、牧師、心理療法士、大学教授の話をしたが、その間に忘れてはならない存在、お方がいらっしゃるのだと思う。
特にこの受難節という季節にあって。私たちはヨハネ3:16をよく読む。「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」しかし、本当に神がどのように私たちに永遠の命を与えられているのかよく考える必要があるのだと思う。
神の子は一人の弟子に裏切られ、他の弟子たちからも置き去りにされ、兵士から鞭でうたれ裸にsれ、人々から十字架にかけろとののしられ、本当に十字架に架けられ殺された。
しかし、イエスの話はそれで終わらなかった。イエスは今でも聖霊として生きておられ、私たちと共にいてくださり、真っ暗闇でもいっしょに歩まれる。どんな暗闇にも夜明けがあり、希望がある。私たちの終わりには、あらたな命のはじまりがある。
残りの受難節、みなさんが良く眠れるようにとは祈る。しかし眠れない時があっても心配しないように。それを無視したりすることはかえってよくないのではないだろうか? 主に祈り、イエスに助けを求めよう。聖霊とともにおられるイエスが、常にいっしょにいてくださり、私たちを決して見捨てるようなことはなさらない。アーメン 安達均
Sleepless Nights John 3:14-21
Pr. Hitoshi Adachi
May Grace and Peace come to you in the name of Jesus Christ, our Redeemer and Lord!
Until I finished my first year of seminary education, I was still working for a medical device company. Their most popular product, in the US market, was the electroencephalograph.
It’s a device that detects patients’ brainwaves, saves them to the memory, and allows a doctor to analyze them. One of the major purposes of the product was to analyze patients’ sleep patterns and help diagnose sleep disorders.
The need to analyze human’s sleep patterns greatly increased in 90s, because research showed that more than 10 percent of the US population had sleep disorders. Since we were providing the sleep pattern analysis devices, I often attended conferences that sleep researchers and physicians attended.
One thing I learned, in the late 90s, was that almost 70 percent of physicians thought that insomnia cases should be treated as a respiratory issue. Some of you are wearing or have worn breathing masks at night.
However, 30 percent of insomnia cases cannot be cured by respiratory treatments. Physicians discussed the complicated mechanisms that make up a human’s neurological systems.
I tried to follow the discussion, despite having only a basic knowledge of physiology. A Japanese physician, I talked with at that time, said he does not believe that 30 percent of insomnia can be cured by medicine and he prefers not to treat them, because there are so many factors about why people get nervous and cannot sleep.
It is common that when we get to the point we cannot sleep at night, we count numbers or sheep, play very simple games like solitaire, or listen to calming music. A guaranteed sleep aid is listening to my sermons (available on LCR’s website).
How do you deal with sleepless nights? For me, an authentic and good way to deal with sleepless nights is praying. However, if we think about it, to pray one must be alert and awake. St. Paul wrote, “Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart.” (Colossians 4:2) How can prayer help us sleep?
Barbara Brown Taylor wonders, “What if I could learn to trust my feelings instead of asking to be delivered from them. What if I could follow one of my great fears all the way to the edge of the abyss, take a breath, and keep going?
According to the “Diagnostic and Statistical Manual IV”, sometimes called “the psychiatrist’s Bible,” patients grieving the death of a loved one are allowed two months for symptoms such as sadness, insomnia, and loss of appetite. If their grief goes on longer than that, they may be diagnosed with depression and treated with prescription drugs.
Barbara Brown Taylor writes, “Western culture keeps dark emotions shuttered in the dark with other shameful things….” But is it good to just let them go away?
Miriam Greenspan is a psychotherapist and author of Healing Through the Dark Emotions. Her mother is a Holocaust survivor. According to Greeanspan, her mother ACTIVELY grieved for ten years after the war. Greenspan wondered, “Was ten years too long a grief for genocide?”
There are no dark emotions, Greenspan says, just unskillful ways of coping with emotions we cannot bear. The emotions themselves are conduits of pure energy that want something from us: to wake us up, to tell us something we need to know, to break the ice around our hearts, to move us to act.
What people call dark emotions include deep things that people do not want to share or do not want to think about. These feelings may be attributed to fear and shame.
These feelings may cause people to feel uncomfortable socializing with others, cause people to think that “I am not worthy,” or cause people to be vulnerable in spirit due to one’s failure or a particularly sad incident. There are many causes why people become nervous or worried. This anxiety can lead to sleeplessness.
There are many cases in which people believe “I am an insomniac and I need treatment using Western medicine.” Or people think it’s a good idea that to not deal with dark emotions and let them go away. Barbara Brown says people have low tolerance for “the dark emotions.”
Dr. Brené Brown, a professor and researcher on topics ranging from vulnerability, courage, worthiness, and shame. She points out “Vulnerability is the core of shame and fear and our struggle for worthiness but it is also the birthplace of joy and creativity, of belonging, and of love.”
Today, I told stories about one physician, one pastor, one psychotherapist, and one professor, but among those, I believe there is one figure whom we should include and not overlook – Jesus.
Especially during this Lenten season…, we often read the Gospel verse, John 3:16, “For this is how God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.” But I think the real issue is how God, Jesus, saved us and redeemed us. I think we need to think about that.
God’s son, Jesus, was betrayed by one of his disciples, left alone by other disciples, whipped and stripped naked by soldiers, abused by surrounding crowd, and in the end he was crucified and died.
But that was not the end of His story. He is always with us, guiding us and helping us through difficult times. There is a dawn within every darkness and that brings us hope. In our end, there is a new beginning.
During this Lenten season, I hope and pray that you can sleep well, but even if you cannot, do not worry about it too much. It’s not better to ignore your dark emotions and let them go. Instead, pray and let Jesus help you deal with those dark emotions. He always abides with us and won’t abandon us. Amen.
2015年3月15日LCR日本語部週報通算第1344号
March 15, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
今週後半の聖書日課にある詩編107 編1-3節および17-22節を読む。150編ある詩編は、五つのグループに分けてとりあつかわれることがある。その五つのなかで、107編以降150編までは、最後のグループとされる。107編は第五詩編グループの中で一番最初の詩編ということになる。いつものように、主なる神に心を集中させて読んでいこう。そして、気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神は、現代の私たちに何を語っているのか、思いを巡らせよう。
詩編107編
1:「恵み深い主に感謝せよ/慈しみはとこしえに」と
2:主に贖われた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らを贖い
3:国々の中から集めてくださった/東から西から、北から南から。
17:彼らは、無知であり、背きと罪の道のために/屈従する身になった。
18:どの食べ物も彼らの喉には忌むべきもので/彼らは死の門に近づいた。
19:苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと/主は彼らの苦しみに救いを与えられた。
20:主は御言葉を遣わして彼らを癒し/破滅から彼らを救い出された。
21:主に感謝せよ。主は慈しみ深く/人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。
22:感謝のいけにえをささげ/御業を語り伝え、喜び歌え。
さて、どのような言葉がインパクトがあっただろうか?あるいは引っかかったか? わたしの場合は、特に一節の言葉から、恵み深い主から慈しみがとこしえにあるという言葉。
詩編作者の気持ちになって、本日の詩編箇所を振り返りたい。詩編作者の気持ちというべきか詩編編集者の気持ちというべきかよくわからないが、冒頭に書いたように、107編は第五詩編グループの一番最初の詩編。その1-3節は、107編から150編の最大のポイントを詠っているようだ。 主がいかに恵み深いか、そしてその主から注がれる慈しみは永遠に存続している、だから主に感謝せよ(1節)。主は苦しめられている人々を救われた、主に買い戻された人々は皆、感謝して謡え(2節)。主によって東西南北にある国々から集められたものよ(3節)。そして4節以降43節まである長い詩編107編は、主の恵み・慈しみがいったいどのようなものかを具体的に挙げているように思える。その中で今日読んだ17-22節では、詩編作者は以下のようなことを詠っているように思う。 人々は主なる神のことをよくわからず、主に背を向けてしまい罪の道を歩くことになり、結局(神の敵対者)に従う者となってしまった(17節)。どんな食べ物も、本来食べるべきものではない(忌むべき)ものであるため、ほとんど死をさけられない病になってしまった(18節)。そのような苦難の中から主に助けを求めると、主は人々を苦しみの中から救い出された(19節)。 主の御言葉が与えられ、人々は癒され、破滅から救い出された(20節)。だから主に感謝しよう、主の慈しみはとても深く、人々に驚くべき事を成し遂げる(21節)。だから感謝の捧げ物をして、主の成し遂げられた事を代々語り、喜んで主を賛美しよう(22節)。
詩編107編を通して、主なる神は、今日の私たちに何を語りかけてくださっているのだろうか? 昨日3月11日を持って、あの東日本大震災から4年間という期間が過ぎた。四年も経ったのに、仮設住宅にいる方々がいるし、心が癒されていない方々がいるという記事も見るし、四年しか経っておらずまだまだ原発の被害とそれに対処する期間はこれから何十年、何世代にも続くのだという記事も見かける。とくに原発の問題を思う時、17節18節にある言葉は、人々が無知(主なる神を畏れていない状況)であるため、主の道から背いて、悪魔の道を歩み、結果食べるものは、みな汚染されてしまったものとなり、瀕死状態となってしまった、という内容が重くのしかかってくる。しかし19節以降にあるように、主なる神に助けを求めると苦しみから救われ、主の御言葉によって癒され、破滅から救われる。という言葉に大きな望みがあることを覚えたい。そして、人々に主の業を語り伝え、主の永遠の恵みに感謝し、捧げ物をし、賛美しようという言葉から、永遠の慈しみを感じる。そして、この詩編を詠う私たちが、どういう行動をとるべきなのか、自ずとわかってくるように思う。
四旬節にあって、十字架を担いで歩むようになる主を覚え、謙り自分のいたらなさを告白し、聖なる御名を褒め称えつつ。
安達均
父なる神、私の口から出る言葉、メッセージがあなたの思いに適い、そして集まった会衆の一人一人が新しくあなたの思いを見出すことができますように! アーメン
道場という言葉を聞くとどういう印象を持ってもられるだろうか。 剣道、柔道、空手等々のはげしいスポーツをする所と思われている方。 私は高校の授業で剣道を一年間ずっと習った年があった。 高校の道場があり、そこで、週一時間だけだったが、稽古にはげんだ。
いまでも忘れられないことは、最初に道場に入るときは、必ず一礼して入ることが習慣となっていた。それは、私が小さいころから家族で行っていたロシア正教会の会堂に一礼して十字架をきって入っていくが、神聖な場所に入っていくのだという心構えと共通のものがあることを感じた。
あと、もうひとつ忘れられないのは、最初の授業。 50分の授業は、正座してただ、教師から剣道のオリエンテーションを受けたが、一切防具をつけたり、竹刀を持つことはなかった。 50分の授業でやったことは、「正面に礼」 「互いに礼」 という教師の掛け声に従って、お辞儀の練習をする。 そのおじきの練習だけで、一時間が終わった。
そこには、キリスト教で、「主なる神を愛することと、自分を愛するように隣人を愛すること」の大切さを教えられることと共通のものを感じた。 神とも仏とも呼んではいなかったがそこは神聖な場であり、道場の正面におられる大いなる存在に加護されることを願いおじきをし、となりにいる稽古をする相手(戦う相手)に尊敬の念を持っておじきをする。 道場そのもの、生徒たち、そして自分の体も尊敬するように指導された覚えがある。
私の神学校時代の新約聖書の教授、とても影響力のあったMary Hinkle Shore教授は、信仰の道を歩む上で「道場」という言葉を用いて、訓練の大切さを説いている。 あくまで比喩だが、道場に通って練習するように、信仰においても礼拝に通うという約束と礼拝堂を尊敬する大切さがあるのだと思う。
それにしても道場が、今日の聖書の箇所とどういう関係があるか、首をかしげているかもしれないが、説教の後半で気がついていただけると思う。
さきほど読んだ福音書の中で、イエス様はずいぶんと激しい行動をとられている。神殿の境内にいた、牛や羊を鞭でおいはらって、両替人のお金をまきちらして、さらに台をひっくり返されるという行動をとられた。 「こんなものは、ここから運び出せ。」っと大声も出されたのだろう。
ユダヤ人たちは、イエスに、「こんなことまでしてしまって、いったいどうしてくれるのか? どんなしるしをみせてくれるのか?」 ということをいっている。 「しるし」ということばはわかりにくいかもしれないが、おそらくイエスが見せてくれる、奇跡、つまり、今日の聖書箇所の前に出ているイエスが水をワインにするような。だから、境内がめちゃくちゃになっても元通りに直すような奇跡のことを意味したいたのではないかと思う。
それに対するイエスの返事は、「この神殿を壊せ。 三日で立て直してやる。」 とまでいわれる。 後にわかることだが、イエスは十字架に架かって死に葬られても、三日目に復活したわけで、三日で立て直す神殿とは、イエスの体のことを示唆されていた。 さて、ここで、質問したい。 イエスは、当時に立てられていた神殿そのものの存在を否定され、これまでの神殿ではもう礼拝する必要がないということを意味したのだろうか?
その答えは、まず今日の福音書箇所をよく読む必要がある。イエスは「わたしの父の家を商売の家としてはならない。」と言われている。 ここで、「父の家」とはルカの2章で、イエスがまだ少年時代に、父ヨセフと母マリアは過越祭の後に、エルサレムからナザレの帰り道にいたのに、イエスだけは神殿に残っていたことがあった。 ヨセフとマリアに再会したときに、「わたしが自分の父の家にいるのは当たり前だということを、知らなかったのですか。」ということを言っている。
また、マタイ、マルコ、ルカには、今日と同じ場面のところが描写されており、イエスの言葉のなかに、イザヤ56章7節の言葉を引用して、「わたしの家は、祈りの家と呼ばれるべきである。」ということ、つまり、父なる神の家ー神殿ーは祈りの家というイエスの一生を通じての考え方があるのだと思う。
なので、神殿自体を、イエスは否定しているわけではない。 その神殿で行なわれる行為が、商売の家となってしまい、父の家として、また、祈りの家ということを、どこかに置き去りにしてしまったことが問題だった。 しかし、さらにイエスが三日で神殿を建て直すということを言われたところに、イエスの全く新しい概念を提示されていることがある。 イエスの体が神殿、そこには、神殿の概念がぐっと広がってきている。
さあ、いったい今日の福音書から、わたしたちは、このハンティントンビーチにあるResurrection Church の礼拝堂で、毎週毎週、定期的に、神の御言葉を聴き、祈り、礼拝を捧げているが、そのこととどう関係あるのだろうか? イエスはこの礼拝堂で毎週毎週、父の家であり、祈りの家として、礼拝を捧げることを、とても良いこととし、主はわたしたを加護してくださっていると信じている。イエスの体が神殿だと教わっても、毎週日曜の神殿での礼拝は信仰の中心であることには、やはり変わりはないのだと思う。
しかし、わたしたは、同時に、イエスの体が神殿であるということから、普段の生活の中にいてくださる、イエスの存在、聖霊の存在によって、私たちの生活も、そこが神殿になっているということがいえるのだと思う。
コリント信徒への第一の手紙の 3 章 16-17 節には、「あなたがたは、自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちの内に住んでいることを知らないのですか。 (中略) あなたがたはその神殿なのです。」という言葉がある。
さて、私たちの信仰生活のうえで、とても大切なことが、教えられていると思う。 柔道、剣道、空手で、訓練をする道場があるように、わたしたちも、定期的に、つまり毎週日曜日に、聖なる空間、礼拝堂に入り、創造主なる神に出会い、主の御言葉を聞き、賛美する訓練の大切さがある。
それと同時に、わたしたちが世の中に生活するなかで、月曜から土曜も、そこに生きておられるイエスさま、聖霊がわたしたちに宿ってくださっていることを、意識して生活する。 それは、毎週毎週の礼拝堂での訓練によって培われ、わたしたちの体が、神殿となり、普段の生活でも実現するのではないだろうか?キリストに従う者として、神の聖なる場、礼拝堂を愛し敬い、兄弟姉妹を愛し敬う。この礼拝堂は、わたしたちの信仰の訓練をする最高の神の道場という表現もできるのではないだろうか。 主にあって、今週の生活も、ゆたかにみちびかれますように。 アーメン
安達均
Is this Sanctuary a Dojo?
John 2:13-22
May the words from my lips and thoughts in this message be acceptable to you, Lord, and may your grace and peace be poured into each of us!
What kind of impression do you have when hear the word “Dojo”? Do you have a perception that it is the place where people fight each other as a sport? As a high school student, I took Kendo lessons for one year. I practiced in a nearby dojo. I enjoyed practice every week, even though it was only one hour per week.
There are two things that I cannot forget. The first thing is that we always enter the dojo only after bowing. For me this was similar to entering the Orthodox cathedral after I bowed and crossed on my chest. Both customs indicate that you’re entering a holy place.
The other thing that I cannot forget is that during the first class, we listened to the teacher’s lecture for 50 minutes. We did not touch bamboo swords or protective gear…instead when, our teacher wasn’t lecturing, he had us practicing proper bowing technique towards the front of the dojo and bowing to each other.
I thought this is somewhat similar to Christianity, because Jesus said, “Love your Lord and love your neighbors.” That is the most important command. And in the dojo, we bow to the front, in our minds, asking for protection while inside the dojo (a holy place) and bowing to each other, respecting our neighbors. Before we were even allowed to participate in the sport, students were taught to respect the dojo, fellow students, and our own bodies.
One of my influential professors at Luther Seminary, Mary Hinkle Shore, taught us the importance of practicing our faith using the word “dojo.” This is a metaphor, but I do believe that dojo practice and practicing our faith are similar – both involve personal commitment and respect.
You still might wonder how the word dojo relates to the Gospel that I read several minutes ago. I hope you will more clearly realize the relationship between the dojo and the sanctuary by the end of my sermon.
In the Gospel, Jesus reacted intensely. He drove all sheep and cattle out of the temple, poured out the coins of the money changers, and overturned their tables. He probably shouted, “Take these things out of here now!”
The Jewish leaders said to him, “What sign can you show us that gives you authority to do this?” They probably hoped for another miracle, since they already saw the miracle of Jesus turning water to wine that was mentioned just before this temple paragraph. Therefore, they expected Jesus to miraculously restore the temple market.
Responding to their request, Jesus replied, “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” This sentence was understood at a much later date, but he was indicating that the temple was the body of Christ which would be resurrected in three days after crucifixion. Here, I would like to ask a question. Was Jesus denying the temple? Did he mean that no one should worship at the existing temple anymore?
To think about the answer to that question, first we should read the Gospel very carefully. Jesus said, “Stop making my Father’s house a marketplace.” Here, the Father’s house is the same word that Jesus used when he was 12 or 13 years old. In Luke Chapter 2, when Joseph and Mary lost sight of young Jesus while returning to their hometown of Nazareth from Jerusalem; they found Jesus in the temple. Then, Jesus said, “Did you not know that I must be in my Father’s house?”
The other passage is not in John’s Gospel, but the same Temple incident was written in Mark, Luke, and Matthew. According to the other three Gospels, Jesus quoted the words of Isaiah Chapter 56:7, “My house shall be called a house of prayer.” Jesus’ word is consistent that the temple has been always his Father’s house and that it is a house of prayer.
Therefore, I do not think Jesus is denying the temple at all. The issue was what they were doing inside the temple. They were deviating from what they’re supposed to do at a house of prayer. Then, what Jesus said was a completely new concept. He indicated that his body is the temple. The perception of the temple became much broader than it used to be.
What does this mean? What is relevant to our modern lives in the Gospel? The LCR’s sanctuary is where we listen to God’s Word, pray to God, and worship God. While we listen to the Word, when we pray, and when we worship Him in this sanctuary; I believe Jesus still joyfully listens to and protects us. These spiritual practices should always be central to Christians’ lives.
However, at the same time, from what Jesus said, his body is the temple and we should recognize also that in the midst of our lives the Holy Spirit, Jesus, is with us and our body is a temple, as well, because of his existence.
According to First Corinthians Chapter 3 verses 16 through 17, “Do you not know that you are God’s temple and that God’s Spirit dwells in you? If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person. For God’s temple is holy, and you are that temple. “
I believe today we are learning something very important. Like dojo practices are very important for Kendo or other martial arts, , our faith practices in the Sanctuary, the holy place, our temple, are critically important for us as we listen to God’s words, pray to, and praise Him every Sunday.
At the same time, in our lives from Monday through Saturday, it is very important to live intentionally and recognize that our body is also a temple where the Holy Spirit, Jesus Christ, is living within us. This intentional faithful life is realized based upon our spiritual practices during Sunday worship in this sanctuary. As Christians, we learn to respect God’s holy place and our fellow believers. In this way, the sanctuary can be viewed as God’s dojo.
Amen.
Pastor Hitoshi Adachi
2015年3月8日復活ルーテル教会日本語週報通算第1343号
March 8, 2015 LCR Japanese Ministiry English Bulletin
Sunday English Bulletin 1343E(3 Lent)
今週後半に聖書日課にある詩編19 編を読む。いつものように、気になる言葉、あるいはインパクトのあった言葉や節は何かを挙げる。次に、詩編の作者の気持ちになってどのようなことを詠っているか、よく考える。そして神は、現代の私たちに何を語っているのか、思いを巡らせよう。
詩編19編
1:【指揮者によって。賛歌。ダビデの詩。】
2:天は神の栄光を物語り/大空は御手の業を示す。
3:昼は昼に語り伝え/夜は夜に知識を送る。
4:話すことも、語ることもなく/声は聞こえなくても
5:その響きは全地に/その言葉は世界の果てに向かう。そこに、神は太陽の幕屋を設けられた。
6:太陽は、花婿が天蓋から出るように/勇士が喜び勇んで道を走るように
7:天の果てを出で立ち/天の果てを目指して行く。その熱から隠れうるものはない。
8:主の律法は完全で、魂を生き返らせ/主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。
9:主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え/主の戒めは清らかで、目に光を与える。
10:主への畏れは清く、いつまでも続き/主の裁きはまことで、ことごとく正しい。
11:金にまさり、多くの純金にまさって望ましく/蜜よりも、蜂の巣の滴りよりも甘い。
12:あなたの僕はそれらのことを熟慮し/それらを守って大きな報いを受けます。
13:知らずに犯した過ち、隠れた罪から/どうかわたしを清めてください。
14:あなたの僕を驕りから引き離し/支配されないようにしてください。そうすれば、重い背きの罪から清められ/わたしは完全になるでしょう。
15:どうか、わたしの口の言葉が御旨にかない/心の思いが御前に置かれますように。主よ、わたしの岩、わたしの贖い主よ。
さて、どのような言葉がインパクトがあっただろうか?あるいは引っかかったか? わたしの場合は、バイブルスタディをするときや、説教の前などに、15節にある言葉の内容の祈りを心がけていることもあり、15節の「言葉が御旨にかない/心の思いが御前に置かれますように。」
詩編作者の気持ちになって、19編を振り返りたい。 1節にダビデの詩となっているので、ダビデがこの詩編の作者かもしれないし、後世の詩編作者の一人がダビデのことを想像しつつ、礼拝での賛歌として作詩したとも思われる。 2節以降については、本日は、一節一節ふりかえるというより、大きく三つの部分にわけて、ポイントは何かということを述べてみたい。 一つ目は、2節から7節で、天と地、そして太陽の出現について、その空間的、時間的なひろがりを詠っている。2節の「御手の業」や5節の「設けられた」などの言葉からして、天も地も太陽もすべて神の創造のなかでおこっている。 二つ目は、8節から11節で、聖書(旧約聖書でとくにモーセ五書なのだと思う)に書かれ、伝えられてきた、さまざまな主の律法や命令が、いかに尊いもので、畏れおおく、また、金銭には変えられない価値があり、また甘い(愛情に満ちた)ものでもあるか。 三つ目は、12節以降最後までで、主なる神への語りかけ、謙虚な祈りなのだと思う。
詩編19編を通して、主なる神は、今日の私たちに何を語りかけてくださっているのだろうか? 四旬節は3週目に入っている。 この期間、自分の罪を振り返る時期ともいえる。 現代はとかく、自然と離れて、情報化社会の中で人間が作り上げた世界にひたって、生活を送っている。しかし、詩編19編の前盤に詠われていることから、たとえ人間が創り上げたと思われるような世界でも、すべては神の創造の上に成り立っていることを忘れてはならないのだと思う。先週はフロリダ方面へ出張していたが、ダラス経由の飛行機だった。 ダラスという南部に位置する都市でも、行きは空港の滑走路脇に数十センチの雪が溶けずに残っているのに驚いた。そして帰りはなんと、ダラスに雪が降っており、多数の便がキャンセルとなり、私も自宅近くの空港には帰ってこれず、LA国際空港に帰ってきて、予定より7時間遅れで家に日曜の明け方にたどりついた。情報化社会や飛行機の技術がここまで発達しているとはいえ、自然が相手ではどうにもならない。中盤に入って、十戒に代表される主の律法、さらにその大元は、主イエスの御言葉から「主を愛し、隣人を愛する」という最も重要な掟に従って生きることの大切さと、その価値の尊さを覚える。 そして最後の祈りの中に、最重要な掟を、守りきれない私たちの現実があるなかで、神に赦し、清め、導きを願いもとめる私たちの現実があるのだと思う。 アーメン 安達均
マルコ 8:31-38
主の慈しみと平安がここにあつまった一人一人に注がれますように!
ある方が亡くなったために、その方が加入していた日本の生命保険の会社に、死亡を通知して、手続きをはじめてもらうように依頼したことがあった。
すると、保険会社の担当者は「ああ、Mr. Cはクリスチャンだったのに、癌で命を落とされたのね。」と言われた。保険会社の方は、キリスト教に興味を持っておられたようだが、クリスチャンになっていれば、癌にかかったりしない、あるいは癌にかかっても死ぬことは無い、そのようなことを信じている宗教ではないかと思っておられたようだった。
みなさんはどう思っておられるだろうか。 クリスチャンであれば、癌にならないという考えは? 前に説教で話したことがあったと思うが、人生、上り坂あり、下り坂あり、さらにまさかという坂もある。クリスチャンであろうが、なかろうが、まさかもやってくる。
まさかには、いろいろある、がんでステージ4といわれるかもしれない。あるいは突然のストロークか心臓発作か、あるいは突然の交通事故かもしれない。 あるいは、アルツハイマーか、ALSかもしれない。 しかし、肝心なことは、どういう形のまさかが来るかわからないが、どう神と向き合うか、どう家族や友人たちと向き合えるかということではないだろうか?
今日与えられている福音書は、イエスが弟子たちに自分は十字架にかかって殺される。しかし、三日後には復活する話をはじめられたところ。 しかし、一番弟子のペテロは、そんなことがあってはなりませんと言って、イエスをいさめはじめる。
それに対してイエスは、ペテロを「サタンよ引き下がれ」といって叱責する。 サタンとは先週も話したように、人間を神の思いから逸脱させてようとする力。そしてそれにしたがって神の方から別の方向を向いてしまうことを罪と呼んでいる。ペテロは人間の思いとしては当然で、主と仰ぐイエスが十字架にかかって殺されるようなことがあってはならない、そんな「まさか」があってはならないと述べた。
しかし、神の御心はそうではなく、まっこうから、サタンだと否定されてしまった。 じゃ、神の思いはどういうことなのだろうか? イエスは、ペテロを非難した後、とても大切なことを述べていると思う。
「自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、わたしのため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである。 人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。いったいどういうことなのか?」
命という言葉だけで4回、さらに、命をさしている「それ」という代名詞も2回あり、合計、6回の命という言葉があるともいえる。 この命という言葉は、ギリシャ語では、プシュケーという言葉が使われていて、「息」とか文字通り「命」でこの世の命をさしている場合と、「魂」と訳したらよいかと思うが永遠の命をさしている場合がある。
そのどちらの命のことをいっているかを吟味しながら、もう一度読み直したい。「自分の命を救いたい者」の「命」とはどっちか? 「それを失う」の「それ」はどっちか。 「イエスのため、福音のために命を失う」の「命」はどっちか? それを救うの「それ」はどっちか?
答えは、イエスの歩まれた生涯からわかってくる。 イエスのこの世の命は、ユダヤ教の指導者たちばかりではなく、民衆もこぞって、十字架にかけて、この世の命を終わりにしてしまった。 イエスはいっさいそれらに抵抗することなく、従順に十字架を担ぎ、無抵抗のまま、十字架上で死に、葬られた。そして、地獄のようなところにまで行かれた。しかし、イエスは復活し、永遠の命を得る方となった。
イエスは永遠の命に生きておられる方であり、私たちクリスチャンは、イエスの聖霊によって洗礼にあずかった生きるものとなった。それはすなわち、イエスと同じようにわたしたちは、洗礼で罪とともに死に、永遠の命にあずかっている。たとえ、この世の命が終わっても、永遠の命に生き続ける。
問題は、この世の命の終わるときに、どうわたしたちは対応したらよいのだろうか? もちろん、どういう医療が受けられるのか、お葬式も心配、お墓も心配という気持ちもわかるが、もっともっと大切な永遠の命が重要ということをイエス様がおっしゃているのではないだろうか?
この世の命にしがみつくのではなく、たとえ、地獄と思えるようなところを通るかもしれない。ひどい話だが、イエスと同じように、クリスチャンであるがゆえに十字架にかけられて殺される人もたくさんいるのがキリスト教の歴史だ。現代でいえば、イスラム国の兵士たちのテロにあって、命を失うことだってありうる。 しかし、イエスの信仰によって、イエスとともに永遠の命に生きるようにと言われているのではないか。
1ヶ月前は、私は長崎にいた。長崎には、有名な26聖人記念館がある。26聖人のひとりひとりのことは、かなりの記録がのこっておいて名前はもちろん、いろいろなことが紹介されている。 その中の一人、パウロ三木という人は、十字架上で押しかけた群集に向かって、「私はキリスト教を信じたというだけで殺されるのである。この理由のゆえに私は命をささげることをいとわない。私はキリストの教えに従い、自分の処刑を命じた人(豊臣秀吉)と処刑にかかわったすべての人を許したい」と叫んだという。
私は、パウロ三木氏は、たしかにこの世の命は失ったが、永遠の命の中で、イエスととも、今も生きている。 キリストを信じてここで礼拝する私たちも、永遠に命に生き続けていることを覚えて、新しい一週間を新たに歩んでまいりたい。 アーメン
安達均
Those Who Lose Their Lives for the Gospel
Mark 8:31-38
May the Lord’s Grace and Peace be poured into the hearts of the people in this sanctuary!
My friend passed away about 15 years ago. On behalf of his family, I contacted his life insurance company and asked the claims department for guidance because I was the family’s contact person.
The representative said, “Oh I am sorry, even though Mr. C was a Christian, he died due to cancer.” Although the representative showed interest in Christianity, she thought that believing in Christ might prevent you from getting cancer or even if you have cancer, you’ll be Ok and not die due to cancer.
What do you think about the relationship between being a Christian and the possibility of dying due to cancer or any other diseases? I’ve explained in the past, that even if we are Christians, we go through the ups and downs of life, including very difficult times; during which you may miserably suffer.
There are many different types of life challenges. You might be diagnosed with Stage 4 cancer, you might suffer a sudden stroke or a heart attack, or you might be involved in a traffic accident. Also, you or a loved one might be diagnosed with Alzheimer’s disease, dementia, or ALS. When you are forced to deal with these life-changing situations, the issue becomes how do you deal with it – do you accept God’s will or do you act contrary to His will?
In the Gospel text read today, Jesus taught his disciples that he would suffer and be killed by Jewish leaders. However, he also taught that he would be resurrected. Even after listening to Jesus’ teachings, Peter rebuked him.
Jesus responds, to his rebuking disciple by saying, “Get behind me, Peter, Satan!” Satan means, as mentioned earlier, a force causing you to turn away from God’s will, which we call sin. Peter thought, not wrongly, that Jesus shouldn’t have to suffer and be killed. Peter was only human and concerned for his beloved teacher’s safety.
However, what Peter thought was not God’s will. So what was God’s will? I think Jesus said very important things to Peter after rebuking him.
“For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake, and for the sake of the Gospel, will save it. For what will it profit them to gain the whole world and forfeit their life? Indeed, what can they give in return for their life?” What do Jesus’ words mean, to Peter? What do Jesus’ words mean to us?
Here, the word “life” appears four times. Also there are two instances of the pronoun, “it” meaning “life.” As such, the word “life” appears six times. In the Greek Bible, life is the word “pshuke” which has a double meaning. One meaning is “breath and life” which indicates earthly life that is finite. The other meaning is “soul” meaning eternal life; something infinite.
By contemplating which of the two meanings is expressed in each instance of the word “life”, I believe the Gospel will have a deeper impact on your faith journey.
Let me reread this sentence, the words of the Gospel that Jesus taught to his disciples 2000 years ago and teaches to us now. “For those who want to save their life will lose it…” For the first “life”, does he mean earthly life or eternal life? How about “it”, does he mean earthly life or eternal life? “And those who lose their life for my sake, and for the sake of the gospel, will save it.” In the phrase “lose their life,” does he mean earthly or eternal life? How about in the phrase “save it,” does he mean earthly or eternal life?
The answers to these questions may be understood through the life of Jesus Christ. Jesus was crucified not only by Jewish leaders but also by the crowd gathered as witnesses. All agreed to crucify him through their actions or silence. Their choice ended Jesus’ earthly life. Jesus did not fight against the Jewish leaders or against crowd. He just obeyed. He carried the cross, walked to Golgotha, and was crucified. He died and was buried. He even went to the pit. However, he was resurrected after three days. 40 days after the resurrection, he ascended to heaven and is surely living eternal life.
The real issue in our lives is how we face the end of our earthly life. How should we deal with our death? Or how may we better prepare for it?
From Jesus’ words taught to his disciples 2000 years ago and taught to us today, we learn that we should faithfully live for Jesus’ sake, for the sake of the Good News. We are guided to live an infinite eternal life rather than only a finite earthly life. We may encounter devastating hardships, but even in the heavy darkness, like descending to the pit…because of our faith in Christ who also suffered miserably and was crucified, died on the cross on Friday, but then victoriously resurrected on Sunday; we may also live eternal life with Jesus. Sadly, there were many times Christians were killed in the past and they’re still being even now. However even those killed recently are promised eternal life, through faith in Jesus.
One month ago, I visited Nagasaki. There is a famous museum there called the “26 Martyrs Museum.” Each martyr’s name is known and their activities are well recorded. One of them was named Paul Miki. He shouted before he was crucified, saying that “I am going to be killed only because I believed Jesus as our Lord. I won’t miss this earthly life. According to Jesus’ teaching, I forgive Hideyoshi Toyotomi who ordered my death and also forgive the people who are carrying out my crucifixion.
Paul Miki lost his earthly life, but he still lives the eternal life with Jesus. During this Lenten season, let us try not to focus exclusively on our finite troubles and remember the promise of an infinitely better eternal life. In Jesus’ name we pray. Amen.
Pr. Hitoshi Adachi
2015年3月1日LCR日本語部週報通第1342号
March 1, 2015 LCR Japanese Ministry English Bulletin
Sunday English Bulletin 1342E(2 Lent)