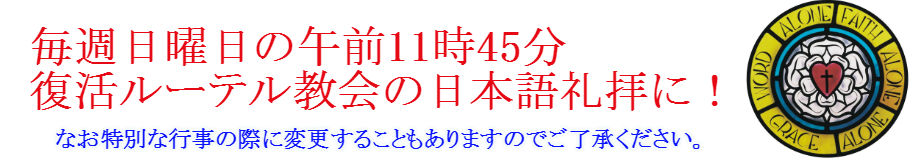ヨハネ2:1-11
主の愛と慈しみが集まった兄弟姉妹に、またこの場に集まれない方々にも豊かにそそがれますように!
カナの婚礼の話。 さきほど、読んだ通り、イエスが水をぶどう酒にするというすごい奇跡をしてくださった。 この話いったいどういう意味があるのか? 私はこの結婚式が、いったいだれの結婚式であるかを仮定、推測次第で、神は実にいろんなことを私たちに語りかけていると思う。
たとえば、この婚礼会場において、マリアは最初から会場にいたが、イエスと弟子たちは、婚礼に招かれたとあった。 これはには母マリアにとって甥とか姪に相当するような親戚の結婚式。 しかし、イエスはいとこかまたいとこ、親戚としての招待だったのかもしれない。 いずれにしろ、この描写からは、イエスの母は、事実上、婚礼を仕切って、給仕の者たちに対してリーダシップをとっていたような気がする。そのような立場のマリアにとっては、ぶどう酒がなくなってしまうというパニックに陥った。
しかし、たとえ心ではパニックと思えるようなことがおこっても、それを外に出さずに、イエスだけに相談する。イエスとの会話はちょっと冷たい感じもしなくもないが、それでもイエスを信頼する。そして、給仕の人々には、イエスに従うようにと告げる。 つまり、マリアの姿勢から、心はパニックでも信仰をもって対処することが、大切なリーダーシップの要素の一つであること教えているという話であるともいえる。
しかし、このカナの婚礼は、本当に、だれの結婚式だか書いていないのだ。 花婿はこの話には登場するが、花嫁は登場していない。 20世紀、21世紀を生きている私たちは、婚礼というと、だれが一番大切だろうか? もちろん司式をする神父や牧師であると思っている人はいないだろう。。。 花嫁が中心人物なわけだが、花嫁がだれかは、まったく書かれていない。
この話が、私たちに語りかけていることは、一体なんなのだろう。 水を最高級ぶどう酒にできるというのは、もちろん魅力的な話で、もし、それが簡単にできるなら、ぶどう酒をお好きな方は、家計も助かるだろうし、それどころか、ぶどう酒ビジネスで教会にすごい献金もできるし、自分の御殿もたつかもしれない。
しかし、問題はそういうことでもなさそうだ。 結婚式というと、カップル誕生のひとつの門出であり、それから家庭生活を築いていく上での、人生の大きなゲートを通ることだ。 そして、この話の中で、だれの婚礼だかが、特定されていないことは、実は、人類のだれの結婚式にも当てはまることを、聖書は語っているのではないかと思う。 それは、主なる神が常に、ともにいてくださるということ。
私は、これまでの牧師生活の中で、お葬式は、いろいろな形で関わってきて、両方の指では数え切れないお葬式の司式している。 しかし、結婚式は、片手の指の本数で数えられるほどの経験しかないが、いつもきまって話すことがある。
それは、結婚式は、いつも二人が結婚するものだが、決して二人だけではなく、絶対的な存在、二人を結びつけて、主なる神が、いつも存在している。 それはたいていの台所には、いつもある玉ねぎの存在のように、実は二人につきそってくださる全知全能なる神がいてくださる。 その神への感謝と賛美を忘れずに、二人で家庭生活を築けますように。
さて、カナの婚礼の話は、実は、同じことをいっているのではないかと思えてくる。 誰の結婚式であろうが、そこに、とても信じられないようなことを起こしてくださる主なる神が、また、励ましを与えてくださる、また苦難をともに体験してくださる、主なる神様が、これからの結婚生活、家庭生活にいつもいてくださることを暗示しているようでもある。
最後に、もっとすごい話をしたいと思う。 私の友人で、40代で妻を亡くした方がいる。 その告別式に際し、彼は、結婚するということは、どんな結婚にも別れも必ず来るということを実感したという。 たしかに、その通りなのかもしれない。
カナの婚礼の話しをしていたのに、葬儀の話になってしまったが、この世の命の終わりというのは、この世に生をもったものには、だれでも来る、間違いのないもの。 そして、そのこの世の最後は、人が扉のこちら側から向こう側に行くとき。 神に会えるとき。 そして、すべての先に召した方々に会えるとき。
旧約聖書、そして、新約聖書にも、神を花婿、夫にたとえ、人類は花嫁、妻にたとえた描写がいっぱい出てくる。 実は先週の後半は聖書日課では、エレミヤ書が読まれ、神が夫、人類が妻のたとえがあった。 本日のイザヤ書では、花婿が花嫁を喜びとするように/あなたの神はあなたを喜びとされる、とある。
本日与えられた福音書、だれが花嫁だか特定されていないカナでの婚礼は、だれであっても、かならずやってくるこの世の死が、実は、神を花婿として、亡くなったものを花嫁とする結婚式であるという要素も生まれてくる。 その時には、私たちが全く想像しえないすばらしい、神の奇跡があり、花婿である神との真の出会いとともに、先に召されたものとの再会も起こる。
安達均
“Whose Wedding?”
Gospel John 2:1 -11
May the Love and Mercy of Jesus Christ be shared with the people in this sanctuary as well as people in the world!
Our Gospel today is the wedding in Cana. As I read a short time ago. Jesus did an unbelievable miracle. What does this story mean? I think depending on who the bride and groom are, we may interpret it so many different ways.
In the beginning part of today’s Gospel, Mary was already there, but Jesus and disciples were invited. It seems Mary was like a mother or aunt and taking on an important host role; said another way Mary was taking on leadership role of all the servants on behalf of the guests. So as the host if there was no wine left, she most likely panic. Even though she was anxious in her heart, she did not show her emotions to the guests and just reported the fact to his son Jesus.
Then, even though the conversation with Jesus was somewhat cold, she just trusted him and then told the servants “Do whatever Jesus tells you.” From this story you might learn an important leadership skill that even in a pinch is helpful, just being quiet and trusting the Lord.
Of the wedding’s details, we do not know whose wedding it was… There is no clear description. Although the groom appeared in this story, it did not say who he was. There is no bride. If it is the 20th or 21st century, the most important person in a wedding is, probably not the pastor who officiate the wedding service, but of course the bride. But again, there is no description of the bride.
What does story really tell us? Of course it is desirable if one can transform water to wine. If you like wine and if you could transform water easily to wine, you can save your alcohol expenses 🙂 and you might also make decent money, so that you may offer more to church. 😉
But what I was focusing on is maybe not the important issue. What do you think about a wedding? It is the “official” start of a couple, husband and wife. Also you may say it is the start of a family. Since the names of the husband and wife were not disclosed, I think God is trying to teach us about a much more important matter which should be common sense in this world: God is always with us.
During last three years, I’ve officiated more than 10 funerals for both Japanese and English speaking members. But I’ve officiated only four weddings. In those four times, I have been always talking about the same important matter.
Although the wedding service is for a husband and a wife to become one, there is not only those two but also the absolute presence of the Lord, who brought the two together and will be with them always. It is something like an onion in the kitchen; He is ever-present. God always walks with you. And I always recommend couples to give thanks and praise to the Lord.
I say that the story of Cana is giving us the same message. Regardless of whose wedding it was, in the midst of the new wedding, there is almighty God who has tremendous power, who encourages people in happy and sad times and is with couples in all seasons of their relationship. He is with families during happy times and difficult times.
To conclude today’s message, I would like to talk about a different aspect of a wedding. A friend of mine lost his wife in her mid-40s. At the funeral, he mentioned that he realized that in any marriage, there will be a time of separation, and that is most probably either spouse’s funeral.
Although we were talking about the wedding in Cana, my message is now talking about a funeral or about funerals in general. It is true that every individual experiences earthly death. When we die, we go through the gate from this side to the other side. That is the time that one can see God and see all the people who have gone to the other side of the gate.
In both old and new testaments, there are descriptions that God is groom, the husband, and that all humans together are the bride, the wife. The first reading today, Isaiah 62:5, reads, “as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you.”
In the Gospel text today, there is nothing clear about whose wedding it was. There is a time for earthly death, and in that moment of earthly death, we may say God as bridegroom welcomes the deceased as bride. In that moment, God is doing something miraculous which we cannot imagine from this side of the gate. On the other side, the bride may see the bridegroom and also all deceased loved ones again. The Lord be with you always before the gate and after the gate. May you experience the wedding when you get there and see the Lord’s miraculous presence. May you also realize and remember that God is and has always been with you. Amen.
Pr. H. Adachi